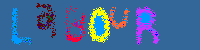 �@
�@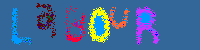 �@�J����@�E�ʘJ���W�@�̂���܂�
�@�J����@�E�ʘJ���W�@�̂���܂�
| �J | �� | �� | �� | �@ | �E | �� | �� | �J | �� | �� | �W | �@ | �� | �� | �� | �� | �� |
| �P | �J���ی�@�̗��j |
| �Q | �J����@ |
�P�j |
�@�Œ�����@ |
�Q�j |
�@�J�����S�q���@ |
�R�j |
�@�J�Еی��@ |
| �R | �J���_��@ |
| �S | |
| �T | �J�������̊m�� |
�P�j |
�@�J����̒����� |
�Q�j |
�@���� |
�R�j |
�@�ēs���ƈᔽ�̐\�����x |
�S�j |
�@�J�����k�E�J���R���� |
| �U | �ʘJ���W�@ |
�P�j |
�@�j���ٗp�@��ϓ��@ |
�Q�j |
�@�玙�E���x�Ɩ@ |
�R�j |
�@�p�[�g�^�C���J���@ |
�S�j |
�@�J���Ҕh���@ |
�T�j |
�@�Ɠ��J���@ |
�U�j |
�@���m�@ |
�V�j |
�@�ٗp���@ |
�W�j |
�@����Ҍٗp����@ |
�X�j |
�@���̑��A�ԐړI�ɂ��J����ɉe����^����@�� |
| �V | �ی��W�@ |
�P�j |
�@�J�Еی��@ |
�Q�j |
�@�ٗp�ی��@ |
�R�j |
�@���N�ی��@ |
�S�j |
�@�����N���ی��@ |
| �@ | HOME�y�[�W |
�P�@�J���ی�@�̗��j
�@1947�N4��7���A�J����@�i�@����49���j�����������B
�@
�@
���a22�N���ߑ�170���u�J����@�̈ꕔ�{�s�̌��v�Ɋ�Â��A���̑啔�������a22�N9��1������{�s�A�c�]�̕��������a22�N���ߑ�227���ɂ�蓯�N11��1������{�s���ꂽ�B
�@
�@
�J����@�́A��O�̂킪���̓���ȘJ�����ɑ��鋭�����Ȃ܂��Ēa�������o�܂�����B���Ȃ킿�A�킪���́A�����㔼�̈ꎞ���A����Ƃ��Đ����E�a�т��x����J���͂�_���̗]��J���͂ɗ����Ă����B
�@
�@
���̎����̂킪���̘J���W�́A�����ԘJ���A�g���S���A��q�����ɂ����āA�㐢�Ɍ��p�����قǂ̑O�ߑ㐫�E�������������Ă����̂ł���A�ߍ��Ȗa�я��H�̘J�����Ԃ��͂��߁A�Y�z�ɂ����邽�������A�l�g�����I�ȔN�G������́A���̈�[���\�w���������̂ɂ����Ȃ��B
�@
�@
���a22�N�̘J����@�ɂ��ẮA�����y�јJ���_��̏͂ɂ�����ꕔ�K��ɂ́A�����J���̋֎~(5��)�A���ԍ��̔r���i6���j�A�_����ԁi14���j�A�����\��̋֎~�i16���j�A�O�؋����E�̋֎~�i17���j�A���������̋֎~�i18���j�Ɍ�����悤�ɁA��O�̔��ȂƗȘJ���W���猈�ʂ��悤�Ƃ���ӎv���ǂݎ���̂ł���B
�Q�@�J����@
�@���@��27���2���́A�u�����A�A�Ǝ��ԁA�x�����̑��̋ΘJ�����Ɋւ����́A�@���ł�����߂�v�ƋK��B���̋K����Đ��肳�ꂽ�@���̒��S�ƂȂ���̂��J����@�i���a22�N4��7���@����47���j�ł���B
�@�S13��121�ӏ��̖{������Ȃ�@���ŁA�J�������ɂ������{�����̐錾�Ɏn�܂�A�J���_��A�����A�J�����ԁE�x���A�x�ɁA���S�q���A�N���ҁA�D�Y�w���A�Z�\�җ{���A�ЊQ�⏞�A�A�ƋK���A��h�ɁA�ē@�ցA�G���A�����ɂ��Ē�߂�B
�@���a60�N�j���ٗp�@��ϓ��@�̐���Ƃ��킹�āA���������i�߂�ꂽ��ʏ��q�ی�K��̓P�p�ɔ����A���a62�N�J�����ԋK��̑�������o�āA���̌�A����10�N�V���ȍٗʘJ�����̓����A15�N�ɗL���J���_��A�ٗʘJ�����A���ًK��Ɋւ���d�v�������s��ꂽ�B
�@����19�N�ɂ͘J���_��@�����肳�ꂽ�ق��A����20�N���ԊO�J���̊������y�єN�x�̎��ԒP�ʕt�^�ɂ��āA�@�������݂č����Ɏ����Ă���B
�@�P�j�@�Œ�����@
�@���a34�N�Œ�����@�̐���ɂ��J����@�̋K�肪�������ꂽ�B���s�A�J����@��28���ɘA�g�E�����K����c���Ă���B
�@�Œ�����@�͈ȉ��̎����𒆐S�ɑ啝�ɉ�������A����20�N7��1������{�s����Ă���B
(1)�@�Œ�����́u���ԁv�ɂ���Ē�߂�B���A�T���͌��̐ݒ�͍폜
(2)�@�n��ʍŒ����-�n��J���҂̐��v��y�ђ������тɒʏ�̎��Ƃ̒���
�@�@
�x�����\�͂��l�����Č���i��9���A�j�B�Ȃ��A���v��̍l���ɓ������ẮA�����ی��Ƃ̐������ɔz���i��9���B�j�B
(3)�@�Œ�����̌��z����-�u�K�p���O�v��p�~���āu���z����v(����)��V�݁B�Ώۂ́A
�@a�@���_�A�g�̂̏�Q�ɂ�蒘�����J���\�͂��Ⴂ��
�@b�@���p���Ԓ��̎�
�@c�@�F��E�ƌP���ł����Č����J���ȗ߂Œ�߂��
�@d�@�y�ՂȋƖ��ɏ]������҂��̑��̌����J���ȗ߂Œ�߂��
�@�i�Œ�����̎��Ԋz��{���ɔ����A�u����J�����Ԃ̓��ɒZ���ҁv�͌��z����̑Ώۂ��珜�O���ꂽ�B�j
(4)�@�h���J���҂̍Œ�����K�p-�h���J���҂̍Œ�����͔h���掖�Ə�̏��ݒn�̍Œ������K�p����i��13���j
(5)�@�J������Ɋ�Â��n��I�Œ�������̔p�~�i���@��11���`��16����3�j
(6)�@����Œ����-�J���Җ��͎g�p�҂̑�\�҂��u���̎��ƎႵ���͐E�ƂɌW��Œ�����v�����肷��悤�\���o�邱�Ƃɂ���Đݒ�i15���j�B
(7)�@�n��ʍŒ�����ᔽ�̔����z�̏����2���~����50���~�Ɉ����グ��ꂽ�i40,42���j�B�܂��A�J���҂̐\���������肳�ꂽ(34��)�B
�@�Q�j�@�J�����S�q���@
�@���a47�N�J�����S�q���@�̐���ɂ��J����@�̋K�肪�������ꂽ�B���s�A�J����@��5�͈��S�y�щq����42���ɘA�g�E�����K����c���Ă���B
�@�ŋ߁A�J�����S�q���@�͈ȉ��̎����𒆐S�ɑ啝�ɉ�������A����18�N4��1������{�s����Ă���B
(1)�@���X�N�A�Z�X�����g�����̐V�݁i28����2�V�݁j
(2)�@�����Ɠ��̉������ݍ�ƌ���ɂ����铝�����S�q���Ǘ�(��ƊԂ̘A������)�i30����2�V�݁j
(3)�@���w�����̐����E�戵�ݔ��ɂ����ĕ���������������Ƃ��d���̒����҂́A�댯�L�Q������t�ɂ���Ē���`�������Ɓi31����2�V�݁j�B
(4)�@���w�����̕\���E������t���x�̉����ƗL�Q�����I���x�̐V�݁i���q��95����6�j
(5)�@���ׂĂ̌��N�f�f���ʂ̘J���҂ւ̒ʒm�i�ςݎc���Č�=���ꌒ�f���ʂ̒ʒm�`����lj��j
(6)�@�����ԘJ���҂ɑ����t�̖ʐڎw�����x�̐V�݁i66����8�C9�V�݁j
�@�@�@[�֘A]���f����[�u�̒lj������i�Y�ƈ�̈ӌ��̈ψ���ւ̕j�A�Y�ƈ�̐E���̒lj��i�K�������j�A�閧�̕ێ��`���̒lj�
(7)�@���S�q���}�l�W�����g�V�X�e���̎��{���Ǝ҂ɑ���v��̖͂Ə��i88�������j
(8)�@�ψ���̒����R�c�����̒lj��A�������S�q���Ǘ��҂̐E���E���S�Ǘ��Ҏ��i�̌������A�E������J���L�������̒lj��i17-19���A10���A11���A60���j
(9)�@�Ƌ��E�Z�\�u�K���x�̌�����
(10)�@�q���Ǘ��ҋy�ш��S�Ǘ��҂́u���Ə�ꑮ�̎ҁv�Ƃ���v���̌�����
�@�R�j�@�J�Еی��@
�@�J�Еی��@�́A���a22�N4��7�����肳��Ă���B
�@�g�p�҂̘J���ЊQ�⏞�ӔC�́A�J����@��8�́i75���`88���j�ɋK�肳��Ă��邪�A�g�p�҂Ɏ��͓����Ȃ��悤�ȏꍇ�A���ۏ�̕⏞���s���Ȃ������ꂪ���邱�Ƃ���A�������g�p�҂��������S���A���{���Ǐ�����ی��u�J���ҍЊQ�⏞�ی��v�ɂ���āA�댯�̕��U��}��A�⏞���m���Ɏ��{�����悤�ɂ��邽�߂ɐ݂���ꂽ�B���݁A�J�Еی��@�́A�u�Ɩ��ЊQ�v�Ɓu�ʋЊQ�v���J�o�[���Ă���B
�R�@�J���_��@
�@
����19�N11���ɐ��������J���_��@������20�N3��1������{�s����Ă���B�J���_��@�́A���@��1���̖ړI�����ɂ��K�肪����悤�ɁA�u�J���_���ӂɂ�萬�����A���͕ύX�����Ƃ������ӂ̌������̑��J���_��̊�{�I�������߂邱�Ƃɂ��A�����I�ȘJ�������̌��薔�͕ύX���~���ɍs����悤�ɂ���v�˂炢���������B�������A�J�g�c�̂̑�\����������c�_�̉ߒ��ł́A�ӌ�������ǂ��Η����鎖���������A�@�����̌����肪���o�����B
�@
�ŏI�I�ɁA�@�������ꂽ�����́A����@�����m�F����`�ŋK�艻���ꂽ����(*1)�A���ُ����̂悤�ɑ��̖@������ڂ�������(*2)�K�肪���S�ɂȂ��Ă���B
�@
�J���_��@�̍\���́A��1�͑����i1-5���j�A��2�͘J���_��̐����y�ѕύX�i6-13���j�A��3�͘J���_��̌p���y�яI���i14-16���j�A��4�͊��Ԃ̒�߂̂���J���_��i16���j�A��5�͎G���i18.19���j�̑S19�ӏ�����Ȃ��Ă���B�J���_��@�́A�������y�юg�p�҂������̐e���݂̂��g�p����ꍇ�ɂ́A�K�p����Ȃ��B
[�Ғ�]
(*1)�@�J���_��@�́A�J�������̕s���v�ύX�ɂ��āA�g�p�҂�����I�ɍ쐬����A�ƋK���ɖ@�I�S���͂�F�߂��ō��ٔ����i��43�H�k�o�X�����j��������A�@�����������A�ꕔ�ɂ́A�g�p�҂�����I�ɍ쐬����i���̂ɋc�_���c���j�A�ƋK���ւ̖@�I�]���𗧖@�ŌŒ艻���Ă��܂������Ƃɂ͍������ᔻ������B
(*2)�@�J�g�̌��͂̌������l�����邱�ƂȂ��A�J���_��Ɋւ��閯���I���[����@�������A���̉����𑽂������W�����Ƃ��Đ��x�����邱�Ƃ��J���ҕی�ɂȂ���Ƃ͌���Ȃ��B�����y�јJ���ē��x����{�Ƃ��āA�@���̗��s�m�ۂ̑[�u���u����J����@�����A���m�ɂ́A���̂��ׂĂ������t�������ł�������ł͂Ȃ��A�����I���[���A���͂��K�肵������������߂Ȃ���A�S�̂��`�����Ă����̂ł���B�J����@�ɋK�肵�A�s���̊ēw�����x�̂��Ƃʼn^�p�������������������҂ł���Ɣ��f�������̂́A�����A�J����@�ɋK�肵�Ă����Ƃ����l���ɗ��̂łȂ���A�J���ҕی�̎����I��ނ������\��������B
�S�@�J�������̊�{����
�@�J����@�́A��1�������7���ɂ����āA���̂悤�ȘJ�������̊�{�������K�肵�Ă���B
(1)�@�J�������̌��茴��
�@�u�J�������́A�J���҂��l����ɒl���鐶�����c�ނ��߂̕K�v���[�����ׂ����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��v�i1���A�֘A���@25���j�܂��A�u���̖@���Œ�߂�J�������̊�͍Œ�̂��̂ł��邩��(�����}��悤�w�߂邱��)�v�i1��2���A�֘A���@27��2���j
(2)�@�J�������̘J�g�Γ��ȗ���ł̌���̌�����
�@�J�������̘J�g�Γ��Ȍ���i2��1���A�֘A�_��@3��1���j�ƘJ������A�A�ƋK���A�J���_��̏���`���i2��2���A�֘A�_��@3��4���j
(3)�@�ϓ��ҋ��y�ђj����������̌���
�@�ϓ��ҋ��̌����́A(�C)�@���ЁA�M���܂��͎Љ�I�g���ɂ�鍷�ʓI�戵���̋֎~=�ϓ��ҋ�(*1)�i3���j�A�i���j�����ł��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��Ē����ɂ��Ēj���ƍ��ʓI�戵�������Ă͂Ȃ�Ȃ�(*2,3)�i4���j�ƋK�肵�Ă���B
�@���̋ϓ��ҋ��̌����́A���̌�́u�j���ٗp�@��ϓ��@�v�i���a61�N4��1���{�s�j�Ƃ��Ĕ��W�A����11�N4���A�y�ѕ���19�N4���̉����{�s���o�č����Ɏ����Ă���B
(4)�@�����J���̋֎~�ƒ��ԍ��̔r���̌���
�@�u�J���҂̈ӎv�ɔ����ĘJ�����������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�i5���A�֘A���@18���j�u���l���A�@���Ɋ�Â��ċ������ꍇ�̊O�A�ƂƂ��đ��l�̏A�Ƃɉ�����ė��v�Ă͂Ȃ�Ȃ��v�i6���j
(5)�@�������s�g�̕ۏ�i7���j
�@�@�߂ɍ�����L����I�����A��I�������͂��߂Ƃ�������Ƃ��Ă̌����̍s�g������ɓ�����ق��A�u���̐E���v�i�c���A�J���ψ���̈ψ��A���R���A���@�R�����A�R�c��̈ψ��A���i271���̏ؐl�A�I������l�A�J���R�����A�ٔ������̐E���j�����s���邽�߂ɕK�v�Ȏ��Ԃ��ۏႳ���B
[�Ғ�]
(*1)�@�J����@��3���́A���ʂɂ�鍷�ʓI�戵�����K�肵�Ă��Ȃ����A����́A�J����@�����蓖���A�����̏��q�ی�������K�肵�Ă�������ł���Ƃ�����B�������A�����ی�̌����P�p���Ȃ��ꂽ����9�N�����i11�N4���{�s�j�ȍ~�ɂ����Ă��A��3���ɐ��ɂ�鍷�ʓI�戵�����K�肳��邱�Ƃ͂Ȃ������B
�@
�Ȃ��A�J����@��3���͋��s�K��ł���A��G����_��͖����A���A������A���Y���ʓI�戵�͑��Q�����ӔC��������Ƃ���ƂȂ�B
(*2)�@�j���������ʂɂ��ẮA�ߋ��A�Ⴆ�A(1)�����\�̒j���K�p���ʁ@(2)�R�[�X�ʐl���Ǘ��@(3)�ꎞ���̎x���W���A��{���̏㏸���@(4)���i���ʂɊ�Â��������ʁ@(5)�Ƒ��蓖�̎x�����ʓ��̌`�ōٔ����̑����ƂȂ��Ă���B
(*3)�@�����ȊO�̐��ɂ�鍷�ʓI�戵���́A�ٔ���́A�j�������戵���̖@�����`������A�����ސE���A���q��N��N������ɂ͒j���ʒ�N���������Ǒ��ɔ��������Ƃ��锻�����ɂȂ����Ă���B
�T�@�J�������̊m��
�@�P�j�@�J����@�̋��s�@�K���ƒ����I����
�@�J����@�́A���炪��߂��J����̊m�ۂ�}�邽�߂ɁA�@���Ɉ��̎d�|�����s�Ȃ��Ă��邪�A���ꂪ��13���̋K�肪���u���s�@�K���v�Ɓu�J���_�@���ɒB���Ȃ����߂ɖ����Ƃ��ꂽ�����ɂ��āA�@���ɒu��������=�����I���́v�ł���B
�@�J����@�̋��s�@�K��
�@
�u���̖@���Œ�߂��ɒB���Ȃ��J���������߂�J���_��́A���̕����ɂ��Ă͖����Ƃ���v�i��13��O�i�����j
�@�����I����
�@�u���̏ꍇ�ɂ����āA�����ƂȂ��������́A���̖@���Œ�߂��ɂ��v�i��13����i�����j
�@�Q�j�@����
�@�������܂��J����@�̗��s�m�ۂ�}���ŁA�d�v�Ȗ������ʂ����Ă���B�J����@�́A��117���`��121���ɍō�1�N�ȏ�10�N�����̒�������30���~�ȉ��̔����܂ł̔������K�肵�Ă���B
�@�J����@�́A���ځA�@���̈ᔽ�s�ׂ��s�Ȃ����s�҂���ق��A�@�l�ɑ��Ă������Y���Ȃ��Ƃ��������̎d�g�݂��̗p���Ă���A������u�����K��v�Ƃ����B
�@�R�j�@�J���ēƈᔽ�̐\�����x
�@����ɁA�J���ē��x�ƘJ���҂̐\�������A�J�������m�ۂɂ����Č������Ȃ�������S���Ă���B
�@�u�J���ēv
�@
�J����@�̊ēs���@�ւƂ��āA�����J���ȘJ�����Njǂ̉��ɁA�s���{���J����-�J����ē��̑̐����~����Ă���B
�ēs���@�ւɂ́A�J����ē����u����A���Ə�̗Ռ��ȂǍs�������̍s�g���s�Ȃ��i101���j�ق��A�J����@�ᔽ�̍߂ɂ��ČY���i�ז@�ɋK�肷��i�@�x�@���̐E�����s�Ȃ��i102���j�B
�@�u�ᔽ�̐\�����x�v�@
�@
�J���҂́A�u���Ə�ɂ��̖@���Ɉᔽ���鎖��������ꍇ�ɂ����ẮA���̎������A�s���������͘J����ē��ɐ\�����邱�Ƃ��ł���v�i104��1���j�A�g�p�҂́A�J���҂��\���������Ƃ𗝗R�Ƃ��ĕs���v�Ȏ戵�����Ă͂Ȃ�Ȃ��i104��2���j�B
�@�S�j�@�J�������̊m�ۂɊ֘A�������̑��̐��x
�@[�P]�@�s���{���J���ǂ̌ʘJ���W�����̑������k����
�@�ʘJ���W�����̉������i�@�i����13�N10��1���{�s�j�Ɋ�Â��A�J���������̑��J���W�Ɋւ��鎖���ɌW��J�g�̕�����v�����K���ɉ������邽�߂̐��x�Ƃ��āA�s���{���J���ǁi�J����ē��j�ɁA�������k�������ݒu����Ă���B
�@���Ăɉ����āA���k�E������s���{���J���ǒ��ɂ�鏕���y�юw���A���������ψ���ɂ�邠�������s���Ă���B
�@[�Q]�@�J���R��
�@�J���R���@������18�N4��1������{�s�������B
�@�J���_��̑��ۂ��̑��̘J���W�Ɋւ��鎖���ɂ��ĘJ�g�Ԃɐ��������������̉�����}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B
�@�J���R���ψ�������҂̐\���Ăɂ�莖����R�����A����̐��������݂������������݁A����̐����ɂ������̌����݂Ɏ���Ȃ��ꍇ�́A�J���R���葱�Ɉڍs����B�\���ẮA��������������̏��ݒn���́A�A�Ǝ��Ə��̏��ݒn���NJ�����n���ٔ����ɍs���B
�U�@�ʘJ���W�@
�@�P�j�@�j���ٗp�@��ϓ��@
�@�j���ٗp�@��ϓ��@�́A���a61�N����{�s����Ĉȗ��A�ٗp�ɂ�����@��ϓ��A�ꐫ���N�Ǘ��̎����S�ہA�Z�N�V���A���n���X�����g�����̕���ɑ傫�ȉe����^���Ă����B
�@�@
�@�@�̖ړI�̂����A���ʋ֎~�̊W���������Ă��A���a61�N���莞�ɂ́u����P���A���������A��N�E�ސE�y�щ��قɂ��āA�����ł��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ������ʂ��֎~�v���Ă�������A����9�N�����i����11.4.1�{�s�j�ł́A�O�L���ʋ֎~�ΏۂɁu��W�A�̗p�A�z�u�E���i�v���������ق��A�|�W�e�B�u�A�N�V�����A�Z�N�V���A���n���X�����g�Ɋւ���K���n�݂��Ă���B
�@�ŋ߂̉����ƂȂ镽��18�N�����i����19�N4��1���{�s�j�ł́A�������ʋ֎~���琫���ʋ֎~�֕��j�̊�{�]�����ʂ����A���ʋ֎~�̑Ώۍ��ڂɁu�~�i�A�E��ύX�A�ٗp�`�Ԃ̕ύX�A�ސE�����A�َ~�߁v��lj������ق��A�Ԑڍ��ʋ֎~�̋K�肪�������ꂽ�B�i�ڍׂ́A��10�͇V���Q�Ɓj
�@�Q�j�@�玙����x�Ɩ@
�@����4�N4��1������{�s���ꂽ�u�玙�x�Ɩ@�v�B����7�N�Ɉ玙�x�Ɩ@�̉����̌`�Łu���x�Ɓv�̖@�����i���x�Ƃ̋`�����͕���11.4.1�B�����ɖ@�������u�玙�E���x�Ɩ@�v�ɉ��́j���}���Ă���B
�@���̌�A�玙�E���x�Ɩ@�́A�Ζ����Ԃ̒Z�k���̑[�u�������i����4�N�A���x�Ƃ͕���11�N�j�ق��A�j�����ʂ̎��ԊO�J���y�ѐ[��J���̐������K�肵�Ă���B
�@����16�N�����ŁA�玙�x�ƁA���x�Ƃ̑Ώۂ��A�ٗp���p�����邱�Ƃ������܂��u���Ԃ̒�߂̂���J���_��v�œ����J���҂ɂ܂Ŋg�傳�ꂽ�B
�@�܂��A�玙�x�Ƃɂ��āA�q���P����1��6�����ɒB����܂ʼn\�ƂȂ�A���x�Ƃɂ��āA�u�ΏۉƑ��P�l�ɂ��A�v����ԂɎ��邲�ƂɈ��A�ʎZ93���܂Łv�Ɗ��ԁE�̏_����}����Ȃǂ��Ă���B�i�ڍׂ́A��6�͇V���Q�Ɓj
�@�R�j�@�p�[�g�^�C���J���@�i����20.4.1�����{�s�j
�@�p�[�g�^�C���J���@�́A�@����ȗ��̑啝�������o�ĕ���20�N4��1���{�s�Ɉڂ���Ă���B
�@��������̃|�C���g�́A�ȉ��̓_�ł���B
�@���ɁA��1���u�@���̖ړI�v������ɂ��킹�ď������������ƁB
�@�]������̓K���ȘJ�������̊m�ۓ��̂ق��u�ʏ�̘J���҂ւ̓]���̐��i�v���������A�u�ʏ�̘J���҂Ƃ̋ύt�̂Ƃꂽ�ҋ��̊m�ۓ���}�邱�Ƃ�ʂ��āv�����̑��i�A�Љ�o�ς̔��W�Ɋ�^����Ƃ��āA�@���̖ړI���������Ă���B
�@���ɁA�p�[�g�^�C���J���҂̏A�ƌ`�Ԃ��A�u�Ɩ��̓��e�y�ѐӔC�v�A�u�l�ފ��p�̎d�g�݂�^�p�v�A�u�_����ԁv�̊ϓ_����ތ^�����A���̏ɉ����āA�ʏ�̘J���҂Ƃ̋ύt������}���Ă������j�m�ɂ��A���̂��߂ɏd�v�Ȃ������̎����ɂ��Ď��Ǝ҂ɋ`�����������Ɓi�ڍׂ́A��11�͇U���Q�Ɓj�B
�@��O�ɁA���̑����̎�������������Ă���B
�@(1)�@�J�������̕�����t�`���Ƃ��āA�J��@15 ���̎����ɉ����A���莖��-�����A�ܗ^�A�ސE���̗L��-�̖������`���t�������Ɓi6 ���P���j
�@(2)�@�ʏ�̘J���҂ւ̓]���̂��߂̑I��I�[�u�`���Ƃ��āA�u��W�����̎��m�v�A�u����@��̕t�^�v��u�]�����x�̐����v�̂��������ꂩ�̑[�u���u����`�����ۂ������Ɓi12���j
�@�S�j�@�J���Ҕh���@�i����19.4.1�����{�s�j
�@�J���Ҕh���́A�u���Ȃ̌ٗp����J���҂��A���Y�ٗp�W�̉��ɁA���A���l�̎w�����߂��āA���Y���l�̂��߂ɘJ���ɏ]��������v�i�h���@2��1���j���̂ł���B
�@�J���Ҕh���ł́A�h���J���҂��h����̎w�����߂̉��ŘJ���ɏ]�����Ă���ɂ�������炸�h����Ƃ̊ԂɌٗp�W�����݂��Ȃ��A������u�ٗp�v�Ɓu�g�p�v����������B
�@�J���Ҕh���̂悤�ȏA�ƌ`�Ԃ́A�J����̊ϓ_����A�u���ԍ��v���̖�肪�����邱�Ƃ�����A�]���͔F�߂��邱�Ƃ̂Ȃ��������̂ł��邪�A�Ȑ܂��o�āA���a61�N�u�J���Ҕh���@�v������{�s���ꂽ�B
�@�J���Ҕh���@�́A��{�ɂ����ċƎҎ���@�ł��邱�Ƃ���A�h���J���҂̘J�������́A�J����@���̓K�p���ی삳���B�Ȃ��A�J���Ҕh���ɂ��ẮA�J���ی�@�̓K�p���u�h�����v�y�сu�h����v�ɁA���ꂼ��œK�p����A���́u�h�����E�h����v�̑o���ɓK�p����邱�ƂƂȂ�A���̓K�p�敪�́A���@��44�`47����2�̋K�肷��Ƃ���ɏ]���i�ڍׂ́A��11�͇T���Q�Ɓj�B
�@�T�j�@�Ɠ��J���@
�@���a45�N10���ɐ��肳�ꂽ�u�Ɠ��J���@�v�́A�Œ�H���A���S�q�����̑��A��Ƃ��āA�Ɠ��J���҂Ɏd�����ϑ�����u�ϑ��ҁv�ɋ`�����ۂ��Ă���B
�@�u�Ɠ��J���v�́A����Ȃǂ���Ə�Ƃ��āA�����E���H�Ǝ҂�≮�Ȃǂ̋Ǝ҂��畨�i�̒��āA��l�Ⴕ���͓����̐e���ƂƂ��ɁA���̕��i�i���͌��ޗ��Ƃ��镨�i�̐�������H���s�����Ƃ������B
�@�Ɠ��J���@���A�����ҊԂ̖��p�̕�����h�~���邽�߁A����̓s�x�A�ϑ������L���̕��y���߂������u�Ɠ��J���蒠�v�́A�L�����y����Ƃ���ƂȂ�Ȃ������B����A�{�@�̕ی�Ώۂł���Ɠ��J���]���Ґ����A�@���������������a45�N�ɂ�201���l�������A����19�N�ɂ�19���l�ւƌ������Ă���i�Ɠ��J���T�������j�B
�@�U�j�@�����̎x���̊m�ۂɊւ���@���i���a51.10.1�{�s�j
�@���Ǝ�ɁA�Г��a���y�ёސE�蓖�̕ۑS�[�u���u���ׂ����Ƃ��`���t���Ă���i3���A5���j�B
�@�܂��A�ސE�J���҂̒����i�ސE�蓖�������j�ɂ��āA�N14.6���̒x�������̎x�������`���t�����i6���j�ق��A��Ɠ|�Y���ɑΉ������̗v�����[������ꍇ�ɂ����āA���������̗��֕����x���^�p����Ă���i7���j�B
�@�V�j�@�ٗp���@�i�J����Ƃ̊W�ł͎���2�_�ɒ��ځA����19.10.1�����{�s�j
�@(1)�@�J���҂̕�W�y�э̗p�ɂ��āA���̔N��ɂ������Ȃ��ϓ��ȋ@���^���Ȃ���Ȃ�Ȃ�(10��)
�@(2)�@�O���l�ٗp�͂̋`�����i���Ǝ�ɂ��ݗ����i�A�ݗ����Ԃ��̑������J���ȗ߂Œ�߂鎖���̊m�F�`���j(28 ��) �O�L�͏o���̖@����b�ւ̒i29 ���j
�@�W�j�@����Ҍٗp����@�i�J����Ƃ̊W�ł͎��̓_�ɒ��ځA����18.4.1�����{�s�j
�@65�Ζ����̒�N�̒�߂����Ă��鎖�Ǝ�́A���N��҂�65�i�i�K�����グ-H19.4.1=63�j�܂ł̈��肵���ٗp���m�ۂ��邽�߁A���̇@����B�̂����ꂩ�̑[�u�i���N��Ҍٗp�m�ۑ[�u�j���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i����18.4.1�����{�s�j
�@�@ ��N�̈��グ�A�A �p���ٗp���x�̓����A�B ��N�̒�߂̔p�~
�@�X�j�@���̑��A�ԐړI�ɂ��J����ɉe����^����@��
�@[�P]�@�J���_�p�@�i����13.4.1�{�s�j
�@
��ƕ����ɔ����J���҂̓]�Г��̃��[�����߂��B
�@[�Q]�@�l���ی�@�i����17.1.1�{�s�j
�@
�J���҂̌l���ی�i���N�Ǘ����E�����^���w���X�֘A��j�̑��ʂ���E��ɊW����v�f���傫���B
�@[�R]�@�s�������h�~�@�i����16.1.1�{�s�j
�@
�ސE�҂̉c�Ɣ閧�̘R����(���@2��1��4���ȉ�)�ɑ���Y�����̓�����}�����B
�@[�S]�@���v�ʕ�ҕی�@�i����18.4.1�{�s�j
�@
���v�ʕ�҂ɑ�����ق��̑��̕s���v�戵�����ւ���K�肪����B���v�ʕ�҂ɂ́A�J���_��㕉���Ă���閧�ێ��`������������邽�߁A���������͂ł��Ȃ����Ɠ��J���Ǘ���̔z�����K�v�ƂȂ�B
�@[�T]�@���̑�
�@
���̑��A�J����̌`���^�p�ɁA���ڊԐڂ̉e����^���Ă���d�v�����Ƃ��āA�Ⴆ�A���@�ɂ�����ٗp�A�������A�s�@�s�ׁA���s���s���ɌW��K��A��Ж@�ɂ�����d�v�g�p�l�i��Ж@10-14���A362��4��3���j�̋K��A�j�Y�E��ЍX���֘A�@�A�E�������i�����@35���ȉ��j�A�E������i���쌠�@15���j�����グ����B
�V�@�ی��W�@
�@�P�j�@�J�Еی��@
�@�{�͂Q�̂R�j�Ƃ��ċL���i�Q�Ɓj
�@�Q�j�@�ٗp�ی��@�i����21�N3��31�������{�s�j
�@�J���҂����Ƃ����ꍇ�y�ьٗp�̌p��������ƂȂ鎖�R���������ꍇ���ɕK�v�ȋ��t�i���Ƌ��t�j���s�����Ƃɂ���āA�J���҂̐����y�ьٗp�̈����}��A���̏A�E�𑣐i������̂ł��邱�ƁB�ٗp�ی��@�ɂ��ẮA���t�����̖������邱�ƂȂ���A�Ƃ��ɒZ���ԘJ���҂̎戵����������(*1)��ی��҂͈̔͂��ǂ����邩�ɂ��āA�c�_�ɂȂ邱�Ƃ������B
�@���t�ł́A�u�玙�x�Ƌ��t�v�u���x�Ƌ��t�v���ٗp�ی�����x������Ă���B
[�Ғ�]
(*1)�@���s�A1�T�Ԃ̏���J�����Ԃ�20���Ԉȏ�A����6�����ȏ�i����22.4.1����́u31���ȏ�v�ɉ���j���������ٗp����邱�Ƃ������܂��҂́A�ٗp�ی��̔�ی��҂Ƃ��Ď戵�����ƂƂ���Ă���B
�@�R�j�@���N�ی��@�@�i�吳11.4.22����j
�@���N�ی��@�́A�u�J���҂̋Ɩ��O�̎��R�ɂ�鎾�a�A�����Ⴕ���͎��S���͏o�Y�y�т��̔�}�{�҂̎��a�A�����A���S���͏o�Y�Ɋւ��ĕی����t���s���v�i���@��1���j�B
�@�J�Еی��@���A�J���҂̋Ɩ���̎��R�ɂ�鎾�a�A�����Ⴕ���͎��S�ɑ��ĕی����t���s���̂ɑ��āA���N�ی��@�́A�J���҂̋Ɩ��O�̎��R�ɂ�鎾�a�A�����Ⴕ���͎��S�ɑ��ĕی����t���s�����̂ł���B
�@�����I�ɂ́A�Ɩ���O�̔��f�A���Ȃ킿�Ɩ���̔��f�ł��邪�A�����J����ē������s���B���̗]�́A�Ɩ��O�̔��f���s��ꂽ���ƂɂȂ邩��A����ɑ��āA���N�ی��@�ɂ��ی����t�����{�����d�g�݂ɂȂ��Ă���B
�@���̂悤�ɁA�J�Еی��@�ƌ��N�ی��@�́A�ɂ߂Ė��ڂȊ֘A����L���邪�A���ی����ʌ��ĕی��ł��邱�Ƃ͕�����Ȃ��A�Ⴆ�A�u�J�Ђ������v�Ƃ��Ė{���Ȃ�Ɩ���ЊQ�ł�����̂��A�Ɩ��O�Ƃ��Č��N�ی��@�ŕی����t���Ă����悤�ȏꍇ�ł́A����𐳂����ی����t�ɖ߂��ɍۂ��ẮA�x���ς݂̌��N�ی��ɂ�鋋�t���A��U�A���Z���ď����ی���J�Еی��@�ɐؑւ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�S�j�@�����N���ی��@�i���a29.5.19����j
�@�����N���ی��@�́A�J���҂̘V��A��Q���͎��S�ɂ��ĕی����t���s���ق��A���I�N�����x��2�K�����ɊY������N�����x�ł�������N�����x�Ɋւ��ĕK�v�Ȏ������߂��@���ł���B
�@�����N���ی��́A���{���A�Ǐ�����i2���j�B
�@�����N���ی��̋����K�p���Ə��́A�@�l,5�l�ȏ�g�p����l���Ə�,�D���ی��@�̑D���ł���B�i5�l�����̌l���Ə�,�l�o�c�Ŕ_�ѐ��Y�A���e���e�A���s�A�ڋq��y�A�@���A�@�����Ƃ́A�C�ӓK�p���Ə��Ƃ���Ă���B�j
�@�܂��A��ی��҂ɂȂ�̂́A�����N���K�p���Ə��Ŏg�p�����70�Ζ����̎҂ł���,�p�[�g�^�C�}�[�͏���J�����ԁA�J����������ʘJ���҂̂����ނ�3/4�ȏ�̎҂ƂȂ�B
(�i�b�j2009�@�w�Y���s�@�u�V���E�J����̖@���v�@���[�o�[�E�C���t�H���[�V�����j
�i��P�́@�J����@�E�ʘJ���W�@�̂���܂��j