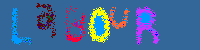 |安全管理者研修|安全管理者の情報|
|安全管理者研修|安全管理者の情報|■HOMEPAGE
■安全管理者選任時研修[労務安全情報センター]
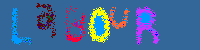 |安全管理者研修|安全管理者の情報|
|安全管理者研修|安全管理者の情報|
■HOMEPAGE
■安全管理者選任時研修[労務安全情報センター]
安全管理者選任時研修
安全管理者資格付与研修
平成18年10月1日以降、安全管理者の資格要件に「厚生労働大臣の定める研修の修了」が付加されました。
「安全管理者選任時研修」・東京開催は、JR総武線「水道橋」徒歩1分で常時開催のレーバー・スタンダード研究所開催セミナーをお奨めします。
(労務安全情報センター)
安全管理者選任時研修は、厚生労働大臣指定カリキュラムに準拠した研修であり、修了証が発行(再発行にも対応)されます。
安全管理者[情報]
(これまで頂いた質問事項への答え,
全部, 載せました)
安全管理者情報小百科 |
|
「ちょっとした」疑問への答えが、全部、載っている |
|
| 安全管理者制度とは、選任を要する「業種・規模」、安全管理者の資格要件、安全管理者の選任要件、安全管理者の職務 | |
| 産業安全の実務経験とは | |
| 安全管理者選任時研修とは | |
| 安全管理者選任報告に際して、窓口では何がチェックされるのか | |
| 常時50人以上使用するという場合の「常時」とは? | |
| 派遣労働者の人数カウントは、どうする? | |
| 安全管理者選任時研修のカリキュラムはどうなっている | |
| などなど | |
| 全部まとめました | |
| 称して、「安全管理者情報小百科」 | |
| ご利用ください | |
| 労務安全情報センター (レーバー・スタンダード研究所) |
「安全管理者」制度とは
| 安全管理者は、事業場の「安全衛生管理体制」の一翼を担い、 | ||
| 事業主によって、一定の業種 (*1)・規模 (*2)の事業場ごとに、資格を有するものの中から(*3)選任され(*4)、事業場において安全に係る事項を管理すること(*5)をその職務とする。 |
戻る
(*1)
安全管理者の選任を要する業種
安全管理者は、安全に係る問題を多く有する業種として法令で指定された次ぎの2の業種該当する事業場において選任しなければならないものとされています。(施行令3条)
1) 屋外産業的業種
2) 工業的業種及び「その他の業種」の一部
(より具体的には、下表参照)
(*2)
安全管理者の選任を要する事業場の規模
常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任しなければならないものです。(施行令3条)
以上(*1、*2)のことは、具体的には、次のとおりとなります。
[表]
| 業 種 | 事業場の規模(常時使用する労働者数) |
| 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 50人以上 |
[関係通達] 改正政令の施行について(平成元年2月28日 基発第89号)
(1) 各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業及びゴルフ場業について、総括安全衛生管理者を選任すべき事業場の規模を常時300人以上(従来は1,000人以上)の労働者を使用する事業場に拡大することとしたこと。
(2) 安全管理者を選任すべき事業者として、(1)に掲げた7業種に属する事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものを加えることとしたこと。
(3) 安全委員会を設置すべき事業場として、(1)に掲げた7業種に属する事業場で、常時100人以上の労働者を使用するものを加えることとしたこと。
(4) (1)に掲げた7業種は、労働基準法第8条8号〔現行別表第1第8号〕又は第14号〔現行=別表第1第14号〕に属する事業であること。
また、これら業種の分類は、原則として、日本標準産業分類をいうものであるが、家具・什器・じゆう器等卸売業は、同分類のの「家具・建具・じゅう器等卸売業」のうち、室内装飾繊維卸売業を除いたもの(家具・建具・じゅう器小売業においても、室内装飾繊維に係る小売業を除く、)を、旅館業は、同分類の「旅館、その他の宿泊所」のうち、簡易宿所、下宿業及びその他の宿泊所(他に、分類されない宿泊所に限る。)を除いたものをいうものであり、また、燃料小売業とは、小分類の「燃料小売業」をいい、ガソリンステーションを含むものであり、ゴルフ場業とは、細分類の「ゴルフ場」をいい、ゴルフ練習場は含まないものであること。
なお、(1) に掲げた7業種のうち卸売業又は小売業とは、商品を実際に取り扱うものをいい、伝票、帳簿上等の取引のみによるものは含まれないものであること。
戻る
(参考事項)
1 「常時使用する」とは
(1) 日雇労働者、パートタイマー等の数を含め、「常態として」使用する労働者の数をいう (昭47.9.18基発第602号)
(2) 常態として使用しているという意味である。したがって、常時は8人であっても、繁忙期等においてさらに2,3人雇い入れるという場合は、含まれない(厚生労働省労働基準局編著「労働基準法上巻」)
2 派遣労働者の取扱い
派遣労働者は、安全管理者の選任においては、派遣先において労働者に参入する取扱いとされています(派遣法45条3項)。
(*3)
安全管理者の資格要件
安全管理者は、その職務を遂行するために必要となる一定の専門的、技術的知識を備え、かつ、作業場の実情をよく知っているものでなければならない。
このような要請に応えるものとして、安全管理者の資格は、原則として、理科系の学歴に加えて産業安全の実務経験を有し、厚生労働大臣が定める「安全管理者選任時研修」を修了したものの中から選任すべきこととされています。(安衛則5条,昭和47労働省告示138号)
戻る
「産業安全の実務経験」とは (昭47.9.18基発第601号の1、平1.2.28基発第89号)
昭47.9.18 基発第601号の1通達(関連部分)
1,2(略)
3 第1号および第2号(現行第1号イ及びロ)の「産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務を含めて差しつかえないものであること。
〔参照=別通達平1.2.28基発第89号〕
安全管理者の資格に係る産業安全の実務については、昭和47年9月18日付け基発第601号の1通達において示しているところであるが、(1)に掲げた7業種(*)については、実務経験として、荷、商品等物の取扱い、運搬等の作業における管理業務を含めて差し支えないものであること。
(*) 各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業及びゴルフ場
(平成元年2月28日 基発第89号)
戻る
「理科系統の正規の過程・学科」とは
昭47.9.18 基発第601号の1通達(関連部分)
1 第1号(現行第1号イ)の「理科系統の正規の課程」とは、学校教育法及び国立学校設置法に基づいて設置された理学又は工学に関する課程、たとえば機械工学科、土木工学科、農業土木科、化学科等を指す趣旨であること。
2 第2号(現行第1号ロ)の「理科系統の正規の学科」とは、学校教育法に基づいて設置された理学又は工学に関する学科たとえば機械科、金属工学科、造船科等を指す趣旨であること。
戻る
安全管理者選任時研修とは
平成18年の「労働安全衛生法」改正により、安全管理者の資格要件に「厚生労働大臣の定める研修の修了」が付加されました。
安全管理者選任時研修の修了要件は、平成18年10月1日から改正施行されましたが、経験2年未満(平成16年10月2日以後選任)の安全管理者にも、同研修の修了が義務付けられました。
| (1) | 厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者 | ||||||
|
|||||||
| (2) | 労働安全コンサルタント |
(平成18年2月24日付、基発第0224004号通達)
戻る
安全管理者選任時研修のカリキュラム
1 安全管理 (3時間)
2
リスクアセスメント・
労働安全衛生マネジメントシステム(3時間)
3 安全教育(1.5時間)
4
関係法令(1.5時間)
(参考) 安全管理者選任時研修の科目・範囲
安全管理者選任時研修は、次の表の科目の欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の範囲の欄に掲げる範囲について行われるもの(施行日前に行われるものを含む。)であること。
|
「旧法で選任された安全管理者」
問 旧法に基づいて選任された安全管理者が同一の企業内で他の工場へ転勤した場合、新法の安全管理者の資格要件を満たすものとみなして差しつかえないか。
答 旧法に基づいて選任された安全管理者が新法でそのまま認められるのは、同一事業内で安全管理の職務をつづける場合に限られるものであり、設問の場合は、新法に定められた資格要件に適合しなければならない(昭47.11.15基発第725号)
戻る
安全管理者の資格の見直し(第5条関係)
安全管理者がその職務を的確に遂行する実務能力を担保するため、厚生労働大臣の定める研修を修了した者であることを安全管理者の資格要件に追加したこと。この資格要件は、労働安全コンサルタント及び改正省令附則第2条にに該当する者を除き、既に選任されている者についても課されるものであること。
併せて、必要となる産業安全の実務に従事した経験年数を、大学卒業(理科系統)では3年から2年に、高校卒業(理科系統)では5年から4年に、それぞれ短縮したこと。(平18.2.24基発第0224003号)
(*4)
安全管理者の選任要件
1) 事業場に専属のものであること
安全管理者は、事業場に専属のものを選任しなければならない(安衛則4条1項2号本文)。
ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合であってその中に労働安全コンサルタントがいるときは、労働安全コンサルタントのうち一人は、専属の者でなくをもよい(前同2号但し書き)
2) 一定の業種・規模の事業場の安全管理者は、そのうち少なくとも一人は他の業務を兼務しない「専任」のものであること(安衛則4条1項4号)。
具体的には次の場合がそれに該当します。
| 業 種 | 事業場の規模(常時使用する労働者数) |
| 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 | 300人 |
| 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 | 500人 |
| 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 | 1,000人 |
| 上記以外の業種(施行令2条1号,2号に掲げる業種であって死傷者数が多い事業場) | 2,000人 |
3) 選任すべき人数
安全管理者については、選任数は法律で定められていない。
ただし、特殊科学設備を設置する事業場であって都道府県労働局長が指定する事業場に限っては、操業中、常時、当該単位における安全管理を行うに必要な人数の安全管理者を選任しておかなければならない(安衛則4条1項3号)。
4) 安全管理者選任報告
安全管理者の選任期限は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に事業場を管轄する労働基準監督署長に行わなければならない(安衛則4条1項1号)
[参考事項]
5)
安全管理者選任報告に添付すべき資格確認資料等について
ア 安全管理者選任報告を行うに当たっては、様式第3号に同様式裏面備考11に記載の書類を添付するほか、免除科目がある場合は当該免除の根拠となる研修、講座等を修了したことを証する書面を併せて添付すること。
イ 様式第3号裏面備考11の「平成18年10月1日において安全管理者として2年以上の経験年数を有する者であることを証する書面(又は写し)」とは、その者に係る過去の安全管理者の選任について事業者が証明したものであること。(平18.2.24基発第0224003号)
「安全管理者選任報告」(安衛則様式3号)
は下記のとおりです。
なお、本様式は、電算処理様式(法令様式)となっていますので、最寄りの労基署から取り寄せを要します。(様式のダウンロード利用はできません)
(*5)
安全管理者の職務
安全管理者の職務について労働安全衛生法は第10条(総括安全衛生管理者)を引用して、当該総括安全衛生管理者の業務のうち安全に係る技術的事項(*)を管理させなければならない(法第10条)としている。
ここでいう総括安全衛生管理者の業務とは、次の7の業務をいう。
この内、三は衛生管理者のその職務とするため、安全管理者の職務は、一〜二及び四〜七の6の業務ということになる。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
六 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
七 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
安全管理者の作業場巡視について
安全管理者は、その職務の一環として作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。(安衛則6条)
(*) 「安全に係る技術的事項」とは、
必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき第10条第1項の業務のうち安全に関する具体的事項をいうものと解すること。(昭47.9.18基発第602号)
安全管理者に対する 「能力向上教育」
(安全管理者等に対する教育等)
第19条の2 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。(法19条の2第1項)
安全管理者の増員・解任命令
安全管理者が、安全管理者としての義務を怠り、かつ、重大災害を発生させた場合などで労働災害を防止するため必要があると認めるときは、労働基準監督署長は、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。(法11条2項)
安全管理者に対する
「再発防止講習」受講の指示
(講習の指示)
第99条の2 都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者(次項において「労働災害防止業務従事者」という。)に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。
戻る
事業場の安全衛生管理体制
(労働安全衛生法が求める安全衛生管理体制の概要)
| a) 事業場が選任を要する各級管理者 | |
1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)は、一定の事業場においては、安全管理者や衛生管理者の選任を義務付けている。 2) さらに、一定の事業場には、安全管理者、衛生管理者を指揮し、安全衛生に関する業務を統括管理する総括安全衛生管理者を置くことを要求している。 (※総括安全衛生管理者には、その事業場におけるトップの者が当たるとされている。) 3) また、事業者は、一定の場合、産業医や作業主任者(※作業主任者は事業場の安全管理体制の一翼を担う位置づけにある(法第14条関係))を選任しなければならない。 4) なお、安全管理者又は衛生管理者を置かない事業場であって一定のものについては、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければならない。 注 〔建設業・造船業のように重層下請関係において事業が実施される場合には、別途、元方事業者においては、統括安全衛生責任者・元方安全衛生責任者を、下請事業者においては、安全衛生責任者を選任する必要があるが、ここでは、説明を省く。〕 |
|
| b) 安全衛生委員会等 | |
事業場における労働災害を防止するために、安全衛生に関する事項を調査審議し、事業者に意見を述べさせるために一定の事業場では、安全衛生委員会を設置しなければならない。 |
|
| c) 労働者の就業に当たっての措置(就業制限等) | |
就業制限(免許等) 労働安全衛生法は、一定の業務については、「免許を有する者」、「一定の技能講習を修了した者」等でなければ就業させてはならないとしている。いわゆる就業制限規定(法第61条)である。就業制限違反には、罰則適用(刑事罰)が厳格に運用されているので事業者はとくに注意が必要である。 |
|
安全衛生特別教育 前項の就業制限のほか労働安全衛生法では、事業者に対して、労働者の就業に当たって、「安全衛生教育の実施」(雇い入れ時、作業内容の変更時、職長就任時、及び一定の危険有害業務従事労働者に対する安全衛生特別教育)の実施を求めています。なかでも、一定の危険有害業務従事労働者に対する安全衛生特別教育の実施は、前項の就業制限に準じた運用取扱がなされることがあるから留意しておく必要があります。 |
|
安全管理者の選任及び職務に関する法規定等について
労働安全衛生法
(安全管理者)
第十一条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
労働安全衛生法施行令
(安全管理者を選任すべき事業場)
第三条 法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。
(注)安全管理者を選任しなければならない業種
『林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業』が該当すること。
労働安全衛生規則
第二章 安全衛生管理体制? 第二節 安全管理者
(安全管理者の選任)
第四条 法第十一条第一項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第二号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三 化学設備(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。
四 次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち?なくとも一人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。
(表=省略)
2 第二条第二項及び第三条の規定は、安全管理者について準用する。
(安全管理者の資格)
第五条 法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当する者で、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校及び職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校を含む。)における長期課程(職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則の
規定による長期指導員訓練課程を含む。)を含む。以下同じ。)を修めて卒業した者で、その後二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後四年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
二 労働安全コンサルタント
三 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
労働安全衛生規則第5条第3号の厚生労働大臣が定める者(昭47.10.2労働省告示第138号)
労働安全衛生規則第5条第3号の厚生労働大臣が定める者は、次のいずれかに該当する者で、同条第1号の厚生労働大臣が定める研修を修了したものとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)
による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門
学校を含む。)における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)
において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に
従事した経験を有するもの
三 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に定める専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるもの(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年労働省令第1号。以下「平成5年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第3の2に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和60年労働省令第23号)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「訓練法規則」という。)別表第1の専門訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)による改正前の職業訓練法(昭和44年法律第64号以下「旧訓練法」という。)第9条第1項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
四 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるもの(旧能開法規則別表第3に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに訓練法規則別表第1の普通訓練課程及び旧訓練法第9条第1項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
五 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程及び旧訓練法第9条第1項の専修訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後5年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
六 7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(安全管理者の巡視及び権限の付与)
第六条 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
[参考事項] 昭和47.9.18基発第601号の1通達
第1項の「その危険を防止するため必要な措置」とは、その権限内においてただちに所要の是正措置を講ずるほか、事業者等に報告してその指示を受けることをいうものであること。(昭和47.9.18基発第601号の1)
第2項の「安全に関する措置」とは、第11条1項の規定により安全管理者が行うべき措置をいい、具体的には、次のごとき事項を指すものであること。(昭和47.9.18基発第601号の1)