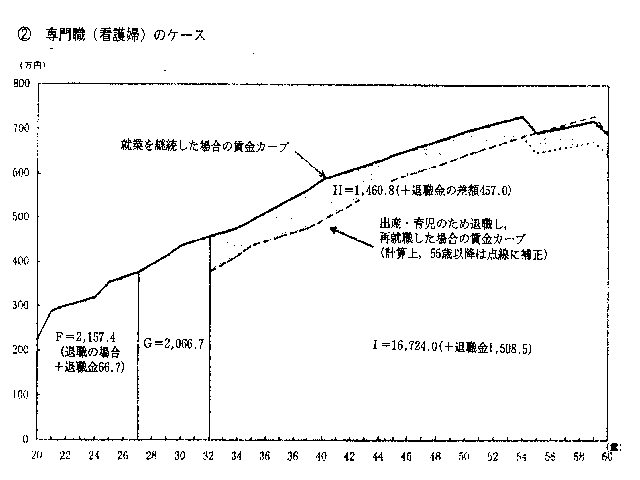1 平成9年の経済企画庁の国民生活白書は、サブタイトルが−−−働く女性 新しい社会システムを求めて−−−。第2章では「働く女性と企業」が取り上げられている。ここでは、その第2節「女性活用の問題点」の部分を抜粋して紹介する。
2 特に、目新しい分析という訳ではないが、日本社会において「出産・子育てによる就業中断」が如何に生涯賃金において不利に働くかについて、「平均的ケース(短大卒)で4,400万円、専門職(看護婦)で1,900万円」と具体的推計を行っているので、ちょっと読んでみようかという気にさせる。
平成9年国民生活白書
第2章 「働く女性と企業」
第2節 女性活用の問題点(抜粋)
1.女性の就業継続,再就職等に関わる問題点
(増加傾向にある働き続けたい女性)
結婚後,あるいは出産後に働き続けることについて,女性はどのように考えているのだろうか。当庁「国民生活選好度調査(以下「選好度調査」)」等による女性のライフコースの理想と現実についてみると「結婚し子供を持ちながら働く」が1992年から97年にかけて理想,現実とも大幅に増加し,理想31.6%,現実23.2%となっている。
また.理想と現実を比較すると「結婚し子供を持ちながら働く」は8.4%,「出産退職し子供が成長したらまた働く」は6.8%と理想に比べ現実が小さくなっているが,これは子育てをしながら働き続けること,退職した後に復職することの難しさをあらわしていると思われる。
(企業も意欲ある人には就業の継続を望んでいる)
企業は.結婚・出産後の女性の就業継続についてどのように考えているのだろうか。企業の意向について労働省「女子雇用管理基本調査」(95年)によると,「女子が結婚や出産後も仕事を続けることについてどのようにお考えですか」という問に対し,9割近くの企業では,女性が就業を継続することを望んでいる。しかし,就業の継続を望む理由については企業規模によって意向が異なり,企業規模が大きいほど「女性の就業意識や仕事を続けられる条件は多様であるので,意欲のある人については結婚や出産後も仕事を続けてほしい」の割合が高いのに対し,企業規模が小さくなるほど「技術や経験を持つ人を確保したいので女性は結婚,出産後も仕事を続けてほしい」の割合が高い。
(女性の転職の理由は仕事とは無関係のものが多い)
女性の20歳代・30歳代での退職・転職の理由の多くが,結婚,出産,育児のためであることは第3章で詳しく述べるが,その他の転職理由について当庁「選好度調査」でみると,男性は「給料が安い」「会社の将来が不安だった」「自分のやりたい仕事ができなかった」等待遇や仕事の内容などによる理由が多いが,女性は「自分の家族の都合」「配偶者の仕事の都合」など仕事とは関係のない理由によって転職をするケースが目立っている。
(女性の活用にあたっての問題点は勤続年数が短いこと)
労働省「女子雇用管理基本調査」により,女性の活用にあたっての問題点を企業の側からみると,最も多いのは「女性の勤続年数が平均的に短い」で,次いで「家庭責任を考慮する必要がある」「一般に女性は職業意識が低い」という順になっている(第4図=省略)。これらは,前述の「男女が同等に活躍できない理由」についての男性の意見とほぼ同じ内容になっていることがわかる。
92年から95年への変化をみると,ほとんどの項目が目立った変化をみせていないが,「女性には法制上の制約がある」が95年に大きく増加しており,実際に女性の活用を考える上で大きな問題となっていることがわかる。
(高い結婚・出産・介護等による退職者の再就職意向)
女性職業財団(現21世紀職業財団)「女子労働者の離職に関する実態調査」(91年)によれば女性の退職者のうちで結婚,出産,育児,介護等を理由に辞めた女性に限ってみれば,9割以上は条件が整えば勤め続けたかったと答えている。
しかし,実際に退職後の再就職の意向を尋ねると,結婚・育児で退職した人のフルタイム志向は非常に低く,育児等が働くための時間的な制約要因となっていることがうかがわれる。「出産とともに退職し,子育てが一段落したら再び勤める」を理想のライフコースと考える女性は多いが,退職後の期間が長くなるほどパートタイム,フルタイムとも再就職の希望は低くなっている。また,出産,育児等のため退職した女性を再度企業が雇用するいわゆる「再雇用制度」を導入する企業が近年増加しているが,退職後再雇用制度が適用される期間や再雇用後の雇用条件の問題に加え,前述の通り,結婚,育児で退職した人のフルタイム志向が低いことなどの理由により制度の利用率は低い。
2.年功賃金体系と女性
(女性にも年功賃金カーブはみられるが,当てはまる人は少ない)
日本の雇用者の賃金は入社直後は低く,その後勤続年数の増加に比例して賃金が上昇していくという,いわゆる年功賃金体系が一つの大きな特徴となっている。大学卒の男女について年齢と賃金の関係についてみると,女性の年齢別賃金カープは,男性のそれと比較してなだらかであるが,男女とも入社後継続して企業に勤務している人の賃金についてみると,女性についても年功賃金カープがみられる。しかし,新卒後入社した企業への残存率をみると,男性は30歳代後半までは低下していきその後横ばいになるのに対し,女性は30歳代前半までに大きく低下し.その後横ばいとなっている。この結果,残存率が男女ともほぼ横ばいとなる40−44歳では,女性の残存率は4.8%であり男性の36.l%と比べ非常に少なくなっている。これまで女性は,結婚,出産等の理由で入社後数年で退職するケースがほとんどであり,新卒後入社した企業に長く勤めることはまれである。したがって,年功賃金体系は女性にも適用されているが,残存率が低いことにより,実際にここで示した年功賃金カーブどおりの賃金を得ている女性はわずかであるというのが現状である。
(出産・子育てによる就業中断・再就職後の賃金格差による金銭的損失額は4干400万円)
前述のように現在のような日本的雇用慣行,特に年功賃金体系の下では,出産・育児等により就業を中断することは多大な金銭的損失をもたらす。その損失額の大きさについて.短大卒相当の女性を例にとり試算してみる。
まず,現在の年功賃金体系が適用されている場合について,労働省「賃金構造基本統計調査」の短大卒の職種計のデータを用いてみると(以下,「平均的なケース」という),就職後出産・子育てなどによる就業中断をせず定年退職まで勤務した場合,第5図におけるA,B,C,D,Eを合わせた賃金が得られ.その総額は約2億1,900万円となる。これに退職金の約1,700万円を含めた約2億3,600万円を生涯で得ることになる。
しかし,結婚後第1子出産時に退職し,子育てが一段落した後に再就職するケースでは,再就職後は賃金が勤続年数が少ないことにより低くなり,上昇カーブも中断なしの場合の賃金カープに比べなだらかになる。この場合の賃金カープを破線であらわしているが.継続して勤務した場合との賃金格差Cは約3,900万円となり、これに退職金の差額約500万円を加えた約4,400万円を失うこととなる。さらに出産・育児による就業中断中の賃金約1,900万円を加えると,出産・育児による就業中断・再就職後の損失額は合わせて約6,300万円となり,賃金の損失率は26.8%となる。
なお,本分析に用いた賃金カープは,労働省「賃金構造基本統計調査」の勤続年数と年齢に基づいているが,再就職時のカープについて45歳から46歳にかけて賃金が低下していたり,57歳以降で上昇しているといった部分で,就業を継続した場合の賃金カープのトレンドと一致しない部分がみうけられる。しかしその部分について補正を行い分析を行った場合でも,賃金の損失率は28.3%となり先ほどの分析と大きな差はみられなかった。
また,就労調整をしながらパートタイマーとして再就職する場合を考えると,パートタイマーの年収分布は,90−100万円で最も多くなっているので,ここでは年収を100万円と仮定すると,賃金カープは図中の点線となり,就業中断時の賃金Bと復職後の賃金格差Cに加え,就業中断・再就職の場合(破線の場合)との賃金格差Dも失うこととなる。さらに退職金を,一度目の退職時に支給される65万円のみであるとすると,就業を継続した場合に比べて,約1億8,500万円の損失が生じ,損失率は78.4%となる。
(1,900万円にとどまる専門職の就業中断・再就職後の賃金格差による金銭的損失額)
次に専門職について看護婦のケースを全国病院労務学会による看護婦のモデル賃金をもとに試算してみる。専門職については,短大卒の平均的なケースで使用した年齢,勤続年数と賃金を組み合わせた信頼性のある統計が乏しく,詳細について正確に把握することは難しい。しかし,一般に専門職の場合,年功賃金カーブは比較的なだらかで,勤続年数の賃金に及ぼす影響は小さいと考えられ,また,退職しても比較的再就職が容易である。そこで,ここでは、再就職時には,退職時と同一の賃金で退職時の職場に復職し,就業継続の場合と比較して5年遅れの賃金で昇給してゆくという仮定を置いて考えてみる。ただし,この場合には,55〜59歳層において,就業中断・再就職後の賃金カープが,就業継続のものを上回ることになるので,以下においては,就業中断・再就職後のケースの55歳以上の賃金について修正を行った上で試算を行っている。
まず,出産・育児の就業中断がない場合についてみると,定年退職までに得られる賃金は,実線で囲んだ部分となり,その総額は約2億2,400万円となる。これに対し出産・育児によって就業を中断した場合には,復職後の勤続年数の差による賃金Hの約1,450万円と,退職金の差額約450万円の合わせて約1,900万円の損失にとどまる。
さらに上の場合と同様に就業中断時の賃金約2,100万円が失われるが.専門職の場合この賃金差Hが上記のケースに比べて小さく,就業中断の場合の生涯賃金は約2億400万円で,就業を継続した場合に比べ約4,000万円のマイナスにとどまり,賃金の損失率は16.3%となる。
先に述べたように,短大卒の平均的なケースとは比較に用いたデータや想定が異なるため,一概には言えないものの,これは平均的なケースの26.8%,28.3%などと比較して小さい。したがって,平均的なケースと生涯所得が変わらないかあるいは,大きな差がない場合,専門職は,女性にとって出産・育児に伴なう就業中断・再就職後の損失が少なく,また,再就職も比較的容易であることなどを合わせて考えると、働きやすい職種である可能性が高い。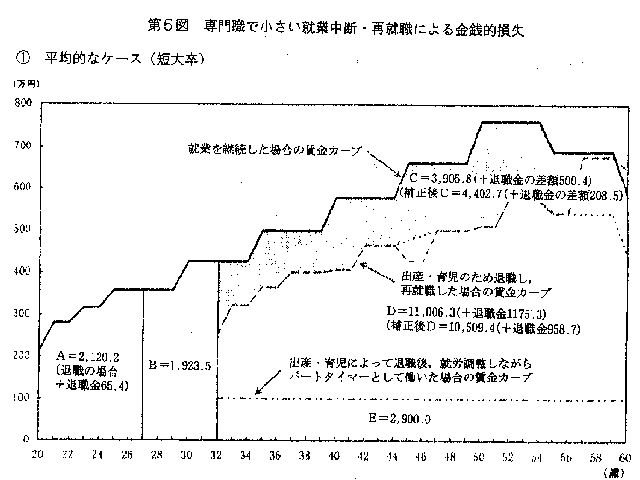
(備考)
1.労働省「賃金構造基本統計調査」(1995,96年),全国病院労務管理学会「病院給与・労働条件実態調査(1996年)により作成。
2.試算に用いた女性は,20歳時に就職。結婚後27歳で第1子を出産し,31歳で第2子を出産する。一時退職する場合には27歳で第1子出産と同時に退職し.第2子が満1歳の時に再就職するものとしている。
3.短大卒の平均的なケースについては「賃金構造基本統計調査」、短大卒の職種計のデータを使用。年間収入については,同調査の96年の「所定内給与額」と推計によって求めた96年の「年間賞与その他特別給与額」により算定。なお,「所定外給与」を考慮していない。
4.短大卒の「年間賞与その他特別給与額」については.95年実績ならびに95.96年の「所定内給与額」の仲ぴ率をもとに推計。
5.看護婦の「所定内給与額」については.「病院給与・労働条件実態調査」の標準者モデル賃金を使用し.年齢刻みのない部分については,線形に補完している。
6.看護婦の継続勤務の場合の「年間賞与その他特別支給額」は.同一年齢の短大卒の継続勤務の場合の「年間賞与その他特別支給額」の「所定内給与額」に対する比率によって算定。
7.27歳時の退職金については日本経営者団体連盟「平成6年9月度退職金・年金実態調査」の全産業・規模計の管理・事務・技術労働者の自己都合退職の標準者退職金をもとに算定。短央卒、看護婦とも退職時の所定労働時間内賃金の3カ月分で計算。
8.60歳時の退職金については27歳時と同資料の会社都合退職の標準者退職金に基づき,就業を継続した場合については所定労働時間内賃金の45カ月分.再就職した場合については35カ月で計算。
9.平均的なケースの「出産・育児のため退職し,再就職した場合の賃金カープ」における点線は,45,46歳,ならびに57歳以降の賃金を「就業を継続した場合の賃金カープ」のトレンドに合わせて補正したもの。
10.「専門職(看護婦)のケース」における点線は、「出産・育児のため退職し,再就職した場合の賃金カ一ブ」が55〜59歳層で「就業を継続した場合の賃金カープ」を迫い越してしまうため、55歳以降の貸金を「就業を継続した場合の賃金カープ」のトレンドに合わせて修正したもの。