【資料のワンポイント解説】
1.労働省(政策調査部)に設けられた人事・労務管理研究会(座長 稲上毅 東京大学文学部教授)の「企業経営・雇用慣行専門委員会」が、このほど発表した中間報告である。分析のもととなった調査は、平成11年2〜3月に行われた従業員規模1,000人以上の大企業2,370社。(有効回答690社、回収率は29.1%)。
2.この「中間報告」を通読した限り、特に目新しい分析があるという訳ではないが、21世紀を目前にした現在おいて、日本の大企業の「経営、人事、労使関係」の動向を−−変わっていくもの、変わらないもの−−という視点から、整理している。
企業の人事担当取締役等には、通読価値の高い資料といえるかも知れない。
3.本資料原文は、以下の労働省記者発表資料のページから転載したものです。図・表は掲載を省略していますので、できるだけ、労働省ホームページと併せて参照されるようお奨めします。
http://www.jil.go.jp/kisya/daijin/990621_01_d/990614_02_d.html
人事・労務管理研究会
企業経営・雇用慣行専門委員会(中間報告)平成11年6月
目次
I はじめに
II 調査結果の内容
1.経営改革
2.コーポレート・ガバナンス
3.人事戦略
4.労使関係
III まとめ
1.経営とコーポレート・ガバナンス 〜変化と持続〜
2.雇用慣行と労使関係 〜変化と持続〜
3.持続と変化が示唆するもの
I はじめに
グローバル化、規制緩和の進展、少子・高齢化といった我が国企業をとりまく環境が激変する中で、日本の経営と労働は大きな曲がり角にさしかかっている。その変化の内容がいかなるものであり、その変化を踏まえた対応のあり方はどうあるべきかについて、労働大臣官房政策調査部長の依頼を受け、平成10年2月より人事・労務管理研究会を開催し、2年計画で調査研究を進めている。このたび、人事・労務管理研究会「企業経営・雇用慣行専門委員会」において、その研究成果を中間的にとりまとめた。
本中間報告は、企業経営・雇用慣行専門委員会において実施した「新世紀の経営戦略、コーポレート・ガバナンス、人事戦略に関する調査」(日本労働研究機構への委託調査)の結果をもとに、企業がめざそうとしている経営と労働の方向と今後の企業のあり方について分析したものである。
戻る
II 調査結果の内容
本調査は、今後の経営戦略、人事戦略の改革に重要な役割を担っている経営企画部門責任者に対して平成11年2月から3月までの期間に自記式郵送法によるアンケート調査を実施したものである。対象企業については、従業員規模1,000人以上の大企業2,370社であり、そのうち690社から有効回収がえられた(回収率は29.1%)。
戻る
1. 経営改革
(包括的な経営改革)
現在、多くの企業が経営改革を進めている。最近3年ほどのうちにすでに「実施した」あるいは「検討中」という回答が多かったものには、意思決定者の少数化や諸会議の集約など経営トップの意志決定のスピードアップ(「実施した」49.6%、「検討中」31.3%、合計80.9%。以下は合計のみ)、企業グループ内での連結経営の強化(83.0%)、「小さな本社」の構築(80.6%)、自己責任経営の明確化(73.9%)、関連企業の整理・統合(69.2%)、財務部門の強化充実(65.1%)などがある(図1−1)。これら6つの施策はしばしばワンセットで行われている。それだけ、進行中の経営改革が包括的であることを示唆している。これらに比べて、担当事業部門をもたない役付き取締役制度への転換や経営者の選抜方法の見直しを「実施した」あるいは「検討中」という回答はいずれも25%前後にとどまった。
(変わる経営指標 〜売上高から経常利益へ〜)
こうした包括的な経営改革とパラレルに、重視する経営指標も大きく変わろうとしている。(図1−2−1、図1−2−2)。
第1に、これまでもっとも重視してきた経営指標(1位)は、業種計でみると、売上高(47.2%)、ついで経常利益(27.2%)であった。しかし、これから重視していこうとしている経営指標(同じく1位・業種計)は経常利益(30.6%)、純利益(20.9%)、営業利益(14.2%)などであり、売上高(12.0%)という回答は激減している。また、株主資本利益率をこれらから重視する経営指標の1位にあげたところが10.0%あった(金融保険業では28.8%)。
第2に、こうした重視する経営指標の比重変化には大きな業種差がみとめられる。もっとも重視する経営指標(1位)の「これまで」と「これから」を業種別にみてみると、建設業では売上高(61.7%)から経常利益(41.7%)へ、製造業でも売上高(49.8%)から経常利益(30.2%)へ、卸売業では経常利益(38.9%)から純利益(38.9%)へ、小売業では売上高(58.2%)から経常利益(38.2%)へ、金融保険業では売上高(23.3%)から株主資本利益率(28.8%)へ、サービス業では売上高(55.7%)から経常利益(36.5%)といった比重の変化がみられる。
(社内分社化・子会社化)
包括的な経営改革のなかには社内分社化、子会社化もふくまれる。
第1に、最近3年ほどのうちに社内分社を設けた企業は全体の1割強(12.2%)、今後の予定のあるところが2割強(24.3%)あった。合わせると4割弱になる。同じ期間中に、子会社を設立した企業は5割弱(47.1%)、今後設立を予定しているところが4割(40.9%)あった。
第2に、このうち社内分社化の代表的ケース(設立予定のものをふくむ)についてその業務内容をみてみると、既存事業中心が7割、新事業中心が1割となっている。他方、子会社の代表的事例では新事業中心が4割弱(37.4%)、既存事業中心が6割を占めている。
第3に、これら社内分社、子会社の設立目的はそれぞれなにか。社内分社、子会社いずれの場合にも、第1位には市場の変化に敏感に対応するため、第2位には既存事業部の整理・再編のためという回答であった。しかし3位にランクされたのは、社内分社の場合には従業員の危機意識を徹底させるため(26.2%)、子会社の場合には雇用の受け皿として(26.8%)というものであった。
第4に、これらの社内分社や子会社はどれほどの権限をもっているのか。社内分社の場合、従業員の採用(42.1%)、労働条件の決定(32.3%)、投資決済(30.3%)などについて一定の自主決定の権限をもっている。子会社の場合には、従業員の採用(72.9%)、労働条件の決定(58.7%)、労使交渉の権限(45.3%)が上位3位にあげられ、雇用・労使関係事項についてかなりの権限を付与されていることがわかる。しかし、資金調達の権限(31.1%)、投資決済(27.6%)、役員人事(8.9%)といったものについて子会社は必ずしも大きな権限を与えられていない(図1−3)。このように、社内分社でも従業員の採用や労働条件の決定、投資決済について固有の権限を与えられているケースが3〜4割に達する一方、子会社であるにもかかわらず、資金調達や投資決済、役員人事などについて権限を与えられていないというケースが7割以上にのぼる。
第5に、その労働条件のあり方について、社内分社の場合には、親会社の水準を上回っても業績に応じた労働条件にするのがよい(28.2%)、労働条件は親会社ではなく、同業他社の水準を基準とするのがよい(24.1%)、企業グループ内各社の労働条件はできるだけ同一化するのがよい(23.1%)などとなっている。このように、社内分社の労働条件にかんして当該企業からの自立性が強調されている。子会社の場合には、同業他社基準(38.4%)、業績準拠(31.3%)に回答が集中している(図1−4)。したがって、これら第4および第5点からすると、子会社には雇用・労使関係の領域を中心に社内分社よりも高い自立性が与えられてはいるが――自己責任経営と企業グループとしての連結経営がともに強調される状況にあって――、両者の連続的性格もみとめられる。とくに資金調達や投資決済、役員人事といった点では社内分社と子会社のあいだにほとんど差異はない。
(持ち株会社)
事業持ち株会社を設立する意向があるところは全体の6.5%、また純粋持ち株会社設立の意向をもつところは5.4%、合わせて1割強(11.9%)であった。すでにいずれかの持ち株会社を設立しているところが5.1%であった。設立の意向のないところが73.5%であった。
小括
(イ) いま日本の大企業では包括的な経営改革が進行中である。意思決定者の少数化や会議の集約化などによる経営トップの意思決定のスピードアップ、「小さな本社」の構築、財務部門の強化、企業グループ内での連結経営の強化、自己責任経営の明確化、関連企業の整理・統合といったことがしばしばひとつのパッケージとなって進められている。
(ロ) それにともなって、重視する経営指標にも注目すべき変化が生じている。全体的には「売上高から経常利益へ」といった重視指標のシフトがみられるが、業種によっては、たとえば金融保険業の場合のように、「売上高から株主資本利益率へ」といった大きな変化もみとめられる。
(ハ) 社内分社化・子会社化の動きも活発である。主として、市場の変化に敏感に対応するため、また既存事業部の整理・再編のためである。これら社内分社・子会社の権限についてみると、雇用・労使関係あるいは労働条件決定といった点で親会社からの自立性がめだつ。その自立性は社内分社より子会社で高い。しかし資金調達や投資決済、役員人事といった点では親会社の影響力が強く、子会社の場合でさえ必ずしも自立的でない。
(ニ) 持ち株会社の設立については、すでに設立しているところ、事業持ち株会社を設立する意向があるところ、純粋持ち株会社を設立する意向があるところがそれぞれ5%ほどあり、合わせて15%程度にのぼる。
戻る
2. コーポレート・ガバナンス
日本のコーポレート・ガバナンスはどこまで変わろうとしているか、いくつかの観点からそれを確かめてみよう。
( 経営理念からみた優先的ステークホールダー)
まず、日本の経営はどのステークホールダー(利害関係者)の利益を優先させようとしているのか。
そのため、つぎのふたつの場面を想定してもらい、どのように行動するかを尋ねてみた。(A)「貴社の経営パフォーマンスが中長期的にみた平均的な経営状況からめだってよくなった場合を想定してください。貴社の経営理念に照らして、その収益を何に優先的に配分しますか」と問い、優先度の高いものを3つまで選んでもらった。それとは逆に、(B)「貴社の経営パフォーマンスが中長期的にみた平均的な経営状況からめだって悪くなった場合を想定してください。貴社の経営理念に照らしてどのような手段を講じますか」と問い、同じように優先度の高いものを3つまで選んでもらった。
その結果、(A)については、従業員の給与・賞与を増やす(83.9%)、株主への配当を増配する(78.8%)のふたつが突出して多く、ついで役員報酬を増す(44.2%)となっている。継続的取引先との取引を先方に有利な条件に切り替える(17.1%)、メインバンクとの取引条件を銀行に有利なように切り替える(3.5%)といった回答は少ない。(図2−1−1)
では、(B)はどうか。従業員の給与・賞与を削減する(84.2%)、役員報酬を削減する(84.2%)が同率で並ぶ。そしてその後に、株主への配当を減配・無配にする(60.7%)となっている。また経営陣が交代する(26.8%)という回答のほうが、再就職先の確保のないまま従業員を整理する(8.6%)よりもめだって多い。(図2−1−2)
したがって、ここからみるかぎり、日本の経営を従業員優遇・株主冷遇などと決めつけることはできない。業績のよいときには、経営者に先立って従業員と株主が利益にあずかり、逆に業績が悪くなれば、従業員とともに経営者が自らの報酬をカットする。株主配当を減らすのはその後のことといった経営行動が、少なくとも経営理念としては浮かび上がるからである。
(安定株主)
株主との関係についていえば、第1に、安定株主の「いる」企業が85.4%、「いない」企業が8.6%あった。
第2に、安定株主が「いる」企業について、その安定株主比率(すべての安定株主が保有する株式数の合計を発行済みの株式総数で除したもの)を尋ねたところ、平均は68.6%という高い値になった。この安定株主比率が70%を超える企業が全体の43.3%ものぼった。とくに運輸通信業やサービス業の安定株主比率が高く、それぞれ82.0%、81.2%であった。また上場企業の53.3%にたいして、非上場企業の安定株主比率は9割(89.4%)と高かっ
た。
第3に、最近3年ほどのうちに、財務戦略として安定株主の確保に努めたという企業が全体の半分(48.5%)あった。とくに金融保険業の場合には、その比率が7割(70.8%)に達した。また今後の方針として、安定株主の確保をあげた企業が5割(50.4%)あった。金融保険業ではその比率は72.2%と高い。
(株の持ち合い)
この安定株主のなかには、互いに株を持ち合っているような企業がふくまれる。
第1に、最近3年ほどのうちに、株の持ち合いをどうしてきたか(表2−1−1)。持ち合いを解消してきたというところが14.3%、特に解消して
きたということはないが44.6%、一部ではむしろ株の持ち合いを進めてきたが9.1%、もともと株の持ち合いはないが32.3%であった。サービス業や運輸通信業では、もともと株の持ち合いはないという回答が53.9%、42.9%という高い値になっている。前項もふくめていえば、株の持ち合いが少ないぶんだけ、安定株主比率が高いといった関係がみとめられる。また企業規模が小さくなるほど、非上場企業ほどもともと株の持ち合いはないという回答(それぞれ56.5%、64.5%)が多かった。
第2に、これからの株の持ち合いについては、現状程度でよいが48.1%、現状より減らしたほうがよいが44.9%と回答は二分された。減らしたほうがよいとした回答は卸売業(69.6%)、金融保険業(54.2%)でめだった(表2−1−2)。
第3に、株の持ち合いを減らす、あるいは株の持ち合いは必要ないという理由はなにか。資産効率を高め、連結株主利益率などを改善するため(63.4%)、グローバル・スタンダードにあった経営に変革していくため(47.7%)という回答がめだった。金融保険業では、そうした回答がいずれについても業種平均を上回った。
第4に、最近3年ほどのうちに、非効率的な持ち合い株の解消を進めてきたという企業は2割強(21.9%)にとどまった。しかし、今後については43.8%の企業が解消を進めていくと答えている。このように、本調査対象企業のうち、もともと株の持ち合いがないところが3割にのぼるが、持ち合いのあるところでは、卸売業や金融保険業などを中心に株の持ち合い解消が進む可能性がある。したがって、前項(安定株主)も視野に入れていえば、株の持ち合いは商社や銀行などを中心にある程度解消していくものとみられるが、それは安定株主が必要ない、あるいはなくなることを意味しない。
(株主広報活動と機関投資家の関心)
安定株主は機関投資家が大部分を占めるが、この10年ほどのうちに、経営にとってこれら機関投資家とのあいだに円滑な意思疎通のパイプを維持していくことが重要な課題となってきた。株主広報活動(Investor
Relations)が重視されるようになった。
第1に、機関投資家などにたいする定例化した業績説明会を開いているか。「開いている」が3割強(32.3%)、「開いていない」が半数以上(54.2%)あった。業種別では、卸売業、電気・ガス・水道・熱供給業のちょうど半数の企業が開いている。逆に、サービス業では15.8%と開催率が低い。また企業規模では、大きな企業ほど業績説明会の開催率が高い(1万人以上の企業では70.0%)。
第2に、開いている場合、いつごろから開いているのか。「80年代」が2割(20.2%)、「90年代前半」が3割弱(27.8%)、「90年代後半」が4割強(44.4%)となっており、株主広報活動は90年代になって普及したことがわかる。
第3に、業績説明会に出席するのは誰か。証券会社(97.3%)、投資顧問(86.5%)、金融関係研究機関(70.9%)、生命保険会社(65.9%)、銀行(64.1%)の5つがめだつ。
第4に、業績説明会に出席する機関投資家のうち、外国人投資家はどれほどの割合を占めているか。外国人投資家の割合は1割以下という回答が4割(41.3%)とめだって多い。
第5に、その開催頻度などについては、年に2回が7割弱(66.4%)ときわだって多い。また、1回2時間というところが同じく7割弱(66.8%)にのぼった。
第6に、主催者側からは誰が出席しているのか。担当役員(87.9%)、担当部門の部長・室長(70.0%)、代表取締役会長・社長(55.2%)であった。
第7に、上記の証券会社、投資顧問などの出席者の具体的属性についてみると、証券アナリスト(96.0%)、機関投資家アナリスト(86.1%)、機関投資家ファンドマネージャー(66.4%)などに回答が集中している。
第8に、では、かれらアナリストやファンドマネージャーの関心はなにか。企業の経営戦略(86.1%)、主要商品の事業動向にかんする詳細情報(63.7%)、経常利益(61.0%)の3つであり、大きく乖け離れて、4位に連結株主資本利益率(30.5%)がくる。しかし興味深いことに、これらアナリストやファンドマネージャーは日本的雇用制度の変革(0%)といったことにはまったく関心がなく、企業の社会的責任遂行(0.9%)や取締役会や監査役会の制度改革(2.2%)にたいしても、さらには株式配当性向(10.9%)や株価変動(8.1%)についてもほとんど関心を寄せていない。(図2−2)
このように、アナリストやファンドマネージャーにとって日本の雇用制度や経営組織の改革といったことは関心の外にあり、かれらにとって肝心な問題は(それら制度がどうであれ)企業の経営戦略、主要商品にかんする詳細情報などについて有益な情報を入手しうるかどうかという点にある。ということはまた、かれらが機関投資家の意向を代弁あるいは代表しているとすれば、機関投資家にとって日本の雇用制度がどうなっていくか、あるいは経営組織がどう変わっていくかなどといったことはどうでもよい――ということになる。
(情報開示)
株主広報活動の一部ともいえる、企業からの投資関連情報の開示についてみておこう。
第1に、最近3年間の実績でいうと、アメリカ企業会計基準による開示(5.2%、1万人以上の企業では28.0%。以下も同じ)、アナリスト・機関投資家・格付け機関などへの情報提供の充実(44.6%、82.0%)、一般株主への経営情報・財務情報の開示強化(42.6%、68.0%)、株主資本配当率・配当目標の開示(32.8%、44.0%)、連結子会社等の範囲見直し・時価評価導入など企業会計基準の見直し(39.6%、66.0%)が大企業を中心にして進められた。
第2に、これらのそれぞれについて、今後の取り組み予定があるとした企業の割合は、アメリカ企業会計基準による開示(28.1%)、アナリスト・機関投資家・格付け機関などへの情報提供の充実(57.0%)、一般株主への経営情報・財務情報の開示強化(62.8%)、株主資本配当率・配当目標の開示(47.4%)などとなっており、いずれについても今後の取り組み予定が最近3年間の実績を大きく上回っている。アメリカ企業会計基準による開示をふくめて、大企業を先頭にこれからさらに投資関連情報の開示が進むものとみられる。
(財務戦略)
財務戦略の実績と展望については、
第1に、最近3年間の実績でいうと、「銀行借り入れから社債発行への切り替え促進」が2割強(22.8%、電気・ガス・水道・熱供給業で58.3%)、「銀行借り入れから株式発行への切り替え促進」が6.8%、「非効率的な持ち合い株の解消促進」が2割強(21.9%)、「安定株主の確保」が5割弱(48.4%、金融保険業では69.9%)、「自己株償却の促進」が1割強(11.2%)、「資産流動化の促進」が3割強(32.3%)という結果であった。
第2に、それぞれについて今後の取り組み予定がどれほどあるか。「銀行借り入れから社債発行への切り替え促進」が26.2%、「銀行借り入れから株式発行への切り替え促進」が14.1%、「非効率的な持ち合い株の解消促進」が43.8%、「安定株主の確保」が50.4%(金融保険業が71.2%)、「自己株償却の促進」が30.7%、「資産流動化の促進」が57.5%となっている(図2−3)。
したがって、全体的な傾向としてめだつのは、ひとつには、銀行借り入れから社債発行あるいは株式発行への切り替え促進、つまり間接金融から直接金融への相対比重の変化である。もうひとつは、一方で安定株主(そのなかにはもちろん銀行もふくまれる)を確保しながら、資産の流動化、非効率的な持ち合い株の解消、自己株の償却などを進めていこうという企業の基本的な姿勢である。
(役員人事)
ここで、企業経営に視野を転じてみよう。まず、役員人事の実態はどうなっているか。
第1に、新社長の人選には大株主・親会社の意向が強く働くとしたものは全体の4割(39.4%)、またそのことが望ましいとする回答が3割強(33.6%)あった。これらの回答は企業形態によって大いに異なる。企業グループの子会社・関連会社の場合には、9割以上(91.7%)がそうした実態にあると回答した。もっとも、それが望ましいとみる子会社・関連企業(53.8%)は現状に比べてめだって少ない。
第2に、副社長以下の人事については社長の意向が強く働くという回答は4分の3(75.9%)を占め、またそれが望ましいとするものは減少しているものの、6割(62.0%)を超えた。
第3に、社長をふくむ役員人事に創業者やその親族の意向が強く働くとしたところが2割強(22.0%)、それが望ましいとする回答が17.4%あった。
第4に、社長をふくむ役員人事にはメインバンクの意向が強く働くとした企業はわずかに3.5%、それを望ましいとする企業は17.4%であった。
第5に、常勤監査役(外部監査役を除く)には取締役経験者がなることが多いとした企業は約半数(51.4%)、しかしそれが望ましいとするところは34.9%にとどまった。
第6に、社長や副社長などの経営首脳については、しばしば抜擢人事があるとした企業は15.1%、そうした抜擢人事が望ましいというところは6割(59.6%)とめだって増えている。
第7に、社長や副社長などの経営首脳については、通算何年といったおよその任期が決まっているとした企業は3割(30.6%)、そうした役員定年制が望ましいとする企業が5割(55.2%)を超えた。(表2−2)
したがって、役員人事のあり方をめぐる現状と望ましさの差異に注目していえば、社長のもつ強い人事権についてはいますこし抑制を加えること、常勤監査役に取締役経験者が就くようなことを少なくすること、役員定年制を定着させること、経営首脳の抜擢人事を進めるべきことなどが示唆されている。
(役員処遇などの改革)
すでにこうした改革の動きは始まっており、今後さらにそれに拍車がかかる可能性がある。
第1に、取締役の人数の削減については、最近3年ほどのうちに「実施した」が3割(29.7%)、「検討中」が24.6%であった。実施率は金融保険業で5割(47.9%)にのぼった。
第2に、執行役員制度の導入については、「実施した」が5.4%、しかし「検討中」が3割(29.1%)ほどに達した。実施済みプラス検討中の数字でみると、卸売業や金融保険業などでその値が高い。
第3に、外部取締役の導入では、「実施した」が約2割(19.3%)、「検討中」が14.2%であった。
第4に、相談役・顧問制度の廃止や見直しにかんしては、「実施した」が1割(11.2%)、「検討中」が26.2%であった。実施済みプラス検討中の数字では、卸売業(55.6%)と金融保険業(42.5%)がめだつ。
第5に、役員定年制の導入については、「実施した」が4割(44.1%)、「検討中」が16.1%であった。卸売業での最近3年間の実施率は66.7%と高かった。
第6に、業績査定による役員報酬格差の拡大については、「実施した」が1割強(12.8%)であったが、「検討中」としたところが34.6%にのぼった。実施済みプラス検討中の数字では、この項目についても卸売業が75.0%と高かった。
第7に、ストックオプション制の導入では、「実施した」が5.4%、「検討中」が19.0%であった。この項目についても卸売業(「実施した」が8.3%、「検討中」が33.3%)がめだつ。
第8に、常務会など経営首脳会議の改廃を実施したところが23.9%、「検討中」が21.4%であった。合わせると、「予定なし」(50.0%)とほとんど変わらない。(表2−3)
これらが示唆しているのは、役員の少数精鋭化と業績査定による処遇の強化ということである。
小括
日本のコーポレート・ガバナンスの現状と今後の展望について、どういうことがいえるか。
(イ)経営理念からみた優先的ステークホールダーとしては、まず従業員と株主、その後に経営者がくる。その意味で、従業員重視・株主軽視あるいは従業員優遇・株主冷遇などということはできない。
(ロ)株の持ち合いについては、もともと持ち合いはないというところが3割ほどあった。株の持ち合いがあるところでは、現状維持と解消(卸売業や金融保険業では解消派が多い)がほぼ均等の比重をもっている。
安定株主については、「いる」企業が85.4%、「いない」企業が8.6%あった。安定株主が「いる」企業における安定株主比率(すべての安定株主が保有する株式数の合計を発行済みの株式総数で除したもの)は、平均68.6%という高い値になった。また、今後の方針として、安定株主の確保をあげた企業が50.7%あった。
したがって、この株の持ち合い解消は今後ある程度進むとしても、それは安定株主が要らないということにはならない。むしろ、株の持ち合い解消が進むぶんだけ、安定株主を必要としているとみなされている。
(ハ)その安定株主は機関投資家とかなり重なる。この10年ほどのうちに、多くの企業が株主広報活動に積極的に取り組むようになった。その一環として、年に2回、1回2時間程度の業績説明会が開かれている。会社側から担当役員や担当部長・室長、さらには代表取締役などが、また機関投資家側からは証券アナリスト、機関投資家アナリスト・ファンドマネージャーなどが出席する。
もっとも、かれらアナリストやファンドマネージャーの主たる関心は経営組織や雇用慣行の改革といったことにはなく、もっぱら経営戦略、主要商品の詳細情報、経常利益といったことがらにむけられている。
このほか、最近では一般株主向けもふくめ株主にたいする各種の情報開示が進められており、今後さらにその進展がみこまれる。
(ニ)財務戦略については、間接金融から直接金融への比重の変化が生じている。また、安定株主を維持しながら(そのためにも)、資産の流動化を進め、非効率的な株の持ち合いを解消し、自己株を償却していこうといった動きがみとめられる。
(ホ)経営を担う役員制度などについていえば、現状では、社長が強力な役員人事権をもっている。常勤監査役(外部監査役を除く)には取締役経験者がなることも少なくない。また社長の人選には大株主や親会社の意向もある程度働いている。さらに、経営首脳の任期制も浸透してきている。他方、メインバンクの役員人事権はほとんどない。また役員抜擢人事も多くない。
しかし、これからは、社長の強い役員人事権を抑えながら、役員の抜擢人事を進め、経営首脳の任期制や役員の定年制を導入していこう、また取締役経験者が常任監査役になることを少なくしていくことが望ましい、と考えられている。
こうした動きとパラレルに、今後は役員の少数精鋭化が図られ、業績査定による報酬管理が浸透していく可能性がある。COLOR="blue">
戻る
3. 人事戦略
経営改革とコーポレート・ガバナンスの見直しについては、ふたつの小括に書いたようにそれぞれ要約できる。それでは、本調査のもうひとつの関心事である人事戦略と労使関係についてはなにがいえるか。
(終身雇用)
まず、今後の終身雇用のあり方にかんする基本的な考え方では、「原則としてこれらからも終身雇用を維持していく」が33.8%、「部分的な修正はやむをえない」が44.3%、「基本的な見直しが必要である」が17.1%(もっとも多いのが小売業の25.5%)、「現在も終身雇用になっていない」が3.8%(もっとも多いのがサービス業の8.7%)であった。
このうち、原則的維持と部分的修正を合わせると8割弱(78.1%)になる(図3−1)。この結果からみるかぎり、近い将来、終身雇用慣行が崩壊するとは考えられない。
(定着率)
この終身雇用慣行のゆくえについて、いくつかの正社員労働力銘柄別の今後の定着率見通しという点からみてみよう(図3−2)。
第1に、30歳代前半の大卒男性については、業種計で「高まるだろう」が1割強(12.0%)、「変わらない」が5割弱(47.1%)、「低まるだろう」が3割強(34.3%、製造業44.4%、卸売業41.7%)であった。したがって、やや定着率が低まる可能性がある。
第2に、30歳代前半の大卒女性の定着率見通しはどうか。「高まるだろう」が24.1%(卸売業38.9%)、「変わらない」が45.5%、そして「低まるだろう」が17.5%であった。むしろ、この労働力銘柄の定着率は高まるかもしれない。
第3に、50歳代前半の大卒男性については、「高まるだろう」が15.1%(1万人以上で6.0%)、「変わらない」が63.0%、「低まるだろう」が15.4%(1万人以上で18.0%)となっている。この結果からみるかぎり、巨大企業で定着率がやや落ちるかもしれないが、ほとんどめだった動きは見通せない。
第4に、50歳代後半の大卒男性については、「高まるだろう」が15.1%、「変わらない」が58.0%、「低まるだろう」が19.9%であった。50歳代前半の大卒男性と同じように、巨大企業で定着率がやや落ちるかもしれないが、全体としては大きな変化は見込めない。
(60歳代の雇用機会)
それでは、60歳代の雇用機会について企業はどう考えているか。全体では、「60歳定年後の再雇用・勤務延長を進める」が4割(39.4%、運輸通信業69.6%、小売業58.2%)、「特に60歳代の雇用機会の拡大は考えていない」が32.9%、「企業グループとして60歳代の雇用機会を確保・拡大する」が32.5%、「取引先企業などにたいする50歳代での再就職斡旋を促進する」が16.8%、「61歳以上へ段階的に定年延長する」が7.1%などとなっている(表3−1)。
このように、定年後の再雇用・勤務延長の促進に企業グループとしての雇用機会の確保・拡大を足し合わせると71.9%になる。これまでの実態に比べて――段階的な定年延長という回答こそ少ないが――、60歳代の雇用機会を企業努力を通じて確保・拡大していこうという姿勢がみてとれる。
(年齢・勤続と能力)
年齢・勤続にともなって能力がいかに推移するかについては、調査票には6つの模様図を示し、大卒事務職、大卒営業・販売職、大卒研究開発・技術職それぞれに、年齢・勤続とともにその職業能力はどのように変化するか、もっともよくあてはまる模様図をひとつ選んでもらった。
ちなみに、模様図1、模様図3、模様図5、模様図6はそれぞれの形状は違っているが、年齢・勤続ともに(とくに「能力の低い人」の)職業能力が右肩上がりで推移するというものであり、その意味でこれらを合計した値がひとつの問題になる。他方、その対極にあるのが模様図2であって、「能力の高い人」もまた「能力の低い人」も一定年齢後は能力がともに低下する山型の形状をしている。したがってその回答が多ければ、年功賃金などに(同一職種にとどまるかぎり)重大な影響の生じうる可能性があることを示唆している。模様図4は、「能力の高い人」は右肩上がりで上昇するが、「能力の低い人」の職業能力は一定年齢でピークに達し、その後は屈折的に下降していくというものである。
第1に、大卒事務職の場合、「模様図1」が13.6%、「模様図2」が8.7%、「模様図3」が31.4%、「模様図4」が20.0%、「模様図5」が8.6%、「模様図6」が4.1%、「その他」が13.6%であった。また、模様図1+模様図3+模様図5+模様図6=57.7%となる(表3−2−1)。
第2に、大卒営業・販売職の場合、「模様図1」が9.7%、「模様図2」が6.8%、「模様図3」が33.8%、「模様図4」が20.0%、「模様図5」が6.8%、「模様図6」が2.8%、「その他」が20.1%となっている。模様図1+模様図3+模様図5+模様図6=53.1%となる(表3−2−2)。
第3に大卒研究開発・技術職の場合には、「模様図1」が6.1%、「模様図2」が13.5%、「模様図3」が24.3%、「模様図4」が21.6%、「模様図5」が6.2%、「模様図6」が1.9%、「その他」が26.4%と分布する。したがって、模様図1+模様図3+模様図5+模様図6=38.5%、模様図2+模様図4=35.1%になる(表3−2−3)。
第4に、模様図1から模様図4までの場合、一定年齢後に能力プロフィールの形状が変化する。その一定年齢は「大卒事務職」で平均35.7歳、「大卒営業・販売職」が35.4歳、「大卒研究開発・技術職」でも35.4歳となっている。平均35歳がひとつの屈折点になっているらしい。
このように、いずれの職種についても模様図2のような山型の能力プロフィールを示すという見方が1割前後の比重を占めている。また、模様図4のような一定年齢以降に人材格差が上下方向に拡大するという見方がどの職種についても2割を占める。これら模様図2や模様図4の見方がよく事実を言い当てているとすれば、少なくとも年功秩序を維持することが難しいだろう。さらに、同じ大卒でも研究開発職の場合には、事務職や営業販売職に比べてそのキャリア形成や処遇に問題が生じやすいように思われる。
【模様図】
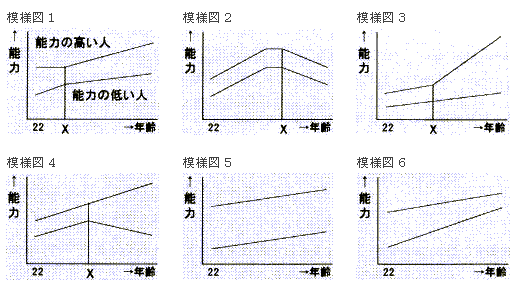
(抜擢人事)
この模様図2や模様図4は抜擢人事(調査票には、「同期でもっとも昇進の早い者が上位年次の者がまだ就いていない役職に先に昇進すること」と定義している)の必要を示唆している。
第1に、本社の課長への昇進にさいして、こうした抜擢人事はどれほど行われているか。
「かなり頻繁に行われている」が1割強(11.7%)、「ある程度は行われている」が5割(49.0%)、「あまり行われていない」が27.0%、「まったく行われていない」が1割(10.3%)という結果であった。
第2に、本社の部長への昇進でも回答結果は似通った分布を示している。
すなわち、「かなり頻繁に行われている」が1割、「ある程度は行われている」が5割(51.7%)、「あまり行われていない」が26.5%、「まったく行われていない」が1割であった。
第3に、本社の取締役への昇進についても、課長昇進、部長昇進の回答分布とほとんど変わらない。
「かなり頻繁に行われている」が1割、「ある程度は行われている」が4割強(44.8%)、「あまり行われていない」が29.0%、「まったく行われていない」が1割強(12.9%)であった。
このように、抜擢人事はある程度行われているが、必ずしも一般的ではない(表3−3)。
(新人事処遇)
もうすこし、人事処遇の細目に立ち入ってみよう。
第1に、つぎの14項目のうち、実施率が高いものから順にあげていくと、
(1)人事考課における評価結果の本人への開示(38.4%、卸売業55.6%)、
(2)本社スタッフの大幅スリム化(32.3%)、
(3)40歳代での取締役就任(26.8%、小売業50.9%、従業員規模1,000人未満43.5%)、
(4)ライン部課長の中途採用(26.4%、サービス業43.5%、1,000人未満も43.5%)、
(5)一般職でのフルタイムの年契約社員の採用(17.7%、小売業36.4%)、
(6)法定外福利厚生費の大幅削減(15.1%)、
(7)企業グループ事業部門や社内分社でのグループ・分社業績にみあった賃金決定(13.2%)、
(8)女性管理職の計画的育成(12.5%)、
(9)文系大学院卒の新規採用(11.7%)
までが回答率10%以上のものである。しかし、
(10)確定拠出型年金(3.8%)、
(11)一般社員の年俸制(3.2%)、
(12)会社派遣でのMBA取得者の優遇(2.2%)、
(13)退職金の前払い制(1.9%)、
(14)役員候補者の30歳代後半での実質的な絞り込み(1.6%)
といった諸項目の実施率はきわめて低い。
第2に、今後3年間でこれら人事処遇はそれぞれどれほど浸透するだろうか。「かなり進む」という回答は順(()内番号は上記の実施率と同じ)に、(1)29.3%、(2)28.0%、(7)11.6%、(5)10.7%、(6)10.4%、(10)8.0%、(8)7.0%、(3)5.9%、(4)4.9%、(11)4.3%、(13)1.6%、(14)1.4%、(12)0.7%、(9)0.6%と並ぶ。このほか、「3年までの有期雇用契約の拡大」(4.2%)、「改正労働基準法による裁量労働制の導入」(13.5%)といった結果になっている。逆に、今後3年間で「あまり進まない」とみられているものに、「会社派遣でのMBA取得者の優遇」(74.3%)、「文系大学院卒の新規採用」(74.3%)、「役員候補者の30歳代後半での実質的な絞り込み」(68.3%)、「退職金の前払い制」(64.8%)、「一般社員の年俸制」(58.8%)、「3年までの有期雇用契約の拡大」(56.5%)、「ライン部課長の中途採用」(52.2%)などがある(図3−3)。
(企業年金)
企業年金制度にかんして、どういう動きがみられるか。
第1に、この数年のうちに「実施した」ものとしては、「運用委託先の変更」(26.7%)、「年金積立金不足分の企業による補填」(25.8%)、「特別勘定など運用方法の見直し」(18.8%)、「年金保険料の増額」(15.7%)、「予定利率(保証利回り)の引き下げ」(13.0%)がめだつが、年金給付額の削減(3.2%)を行った企業はごく少なかった。企業年金制度の廃止に踏み切ったという回答はゼロであった。
このように、この数年をとってみると、長期にわたる極端な低金利という悪条件のもとで、企業は運用先や運用方法を変えるとか積み立て不足分を補填するとか、企業年金制度を維持するため懸命な努力を払ってきた。
第2に、「検討中」の項目としては、予定利率(保証利回り)の引き下げ(45.7%)、特別勘定など運用方法の見直し(36.2%)、年金積立金不足分の企業による補填(33.6%)、年金給付額の削減(32.8%)、年金保険料の増額(29.0%)、運用委託先の変更(28.6%)、企業年金制度の廃止(7.1%)となっている(表3−4)。
ここ数年の取り組みに比べてみれば、より企業年金制度改革への姿勢をもちはじめているようにみえる。
(総額人件費)
一般的に総額人件費を抑えようという企業の姿勢はこの数年のうちにかなり強まった。
第1に、総枠設定を行っている企業は全体の4割強(41.2%)あった。とくに小売業ではその比率は65.5%にのぼった。
第2に、総枠設定をしている場合、それをなにに準拠させているか。多かった順に、「売上高比率」が53.2%、「前年度実績プラス生産性上昇率」が36.6%、「労働分配率」が30.6%、「同業他社の動向」が28.5%などとなっている。売上高が伸びればあるいは生産性が上がれば、総額人件費も多くなるという図式である。
(企業グループ人事管理)
すでにみたように、一方では分権的な自己責任経営が明確化され、他方では企業グループとしての連結経営が強調されている。そのことは人事戦略にも現れている。ここでは、後者の連結経営に関わるいくつかの点にふれてみよう(図3−4)。
第1に、企業グループあるいは連結子会社を包含した総人員計画があるか。「ある」が2割弱(17.1%)、「検討中」が36.4%、ふたつを合わせると5割を超える。
第2に、「連結子会社をふくむ中核企業役員の計画的育成を行っている」が6.5%、「検討中」が38.8%、合計すると45.3%になる。
第3に、「企業グループあるいは連結子会社による企業年金制度がある」という回答が2割(19.4%)、「検討中」が14.9%、合わせると34.3%になる。
第4に、中核企業による連結子会社の採用・配属人事など一元的管理が行われているところが12.8%、「検討中」が28.0%、したがって合計40.8%になる。
これらの結果からみるかぎり、企業グループ連結経営のため企業グループ人事管理も今後かなり進展していくものとみられる。
小括
ここで、人事戦略について小さなまとめをしておこう。
(イ)これからの終身雇用のあり方については、部分的修正という意見が4割強ともっとも多かったが、それに原則的維持の3割強を加えると8割弱になる。したがって、近い将来、終身雇用慣行が崩れるなどということはできない。労働力銘柄別の定着率見通しからみても、労働力の流動化といったシナリオが思い描かれているわけではない。さらに、60歳代の雇用機会にかんしても、段階的な定年延長という考え方こそ少ないが、定年後の再雇用・勤務延長か企業グループとしての60歳代の雇用機会確保・拡大のいずれかを考えている企業が合わせて7割以上にのぼる。特に60歳代の雇用機会の拡大は考えていないという企業は全体の3割強にとどまる。
(ロ) 大卒事務職、大卒営業・販売職、大卒研究開発・技術職別にみた年齢・勤続にともなう職業能力プロフィールについていえば、右肩上がりで推移するものの一定年齢後、「能力の高い人」と「能力の低い人」との格差が拡大するという企業が最も多く、事務職、営業・販売職で3割を占めている。
しかしながら、いずれの労働力銘柄にかんしても、35歳前後で「能力の高い人」「能力の低い人」を問わず下がりはじめるという見方(山型プロフィール)がほぼ1割、同じ35歳前後で「能力の高い人」は上昇していくが、「能力の低い人」は下がっていくという見方が2割を占めた。これらの場合(とりわけ前者)には、年功昇進・賃金は成り立ちにくいだろう。
なお、大卒研究開発・技術職にかんしては、大卒事務職や大卒営業・販売職に比べて山型プロフィールという見方が多かった。
(ハ)「同期のもっとも昇進の早い者が上位年次の者がまだ就いていない役職に先に昇進する」という抜擢人事は、本社の課長、部長、取締役いずれについても、ある程度行われているという回答が5割前後を占めたが、頻繁に行われているという回答は1割にとどまった。あまり行われていない、まったく行われていないを合わせると4割前後になる。したがって、抜擢人事が活発に行われているとみることはできない。
(ニ)新人事処遇ということでは、評価結果の本人開示、本社のスリム化、「若い」取締役の抜擢、ライン部課長の中途採用、フルタイム有期契約社員の採用、法定外福利厚生費の大幅削減などについてある程度の動きが生じている。
逆に、近い将来「あまり進まない」とみられているものに、会社派遣でのMBA取得者の優遇、文系大学院卒の新規採用、役員候補者の30歳代後半での実質的な絞り込み、退職金の前払い制、一般社員の年俸制などがある。
(ホ)企業年金については、この数年のうちに運用先や運用方法の改善、積立金不足分の補填などを行った企業がそれぞれ2〜3割あった。それでも、年金額の削減を行ったところはほとんどなく、企業年金制度を廃止した企業は皆無であった。
しかしこれからは、こうした運用上の改善といった水準を超えた制度改革への動きが出てくる可能性がある。
ちなみに、確定拠出型年金をすでに導入済みという企業は全体の3.8%、また今後3年間でその導入が「かなり進む」という意見は8%にとどまった。
(ヘ)総額人件費管理にかんして、総枠を設定しているところが4割ほどあった。その設定を売上高あるいは前年度実績プラス生産性上昇率などにリンクさせ、したがって売上高や生産性が上がれば人件費総枠も増える、といった運用を行っている企業が多い。
(ト)今後の成長見通しもふくめていえば、新人事管理という意味で企業グループ人事管理の成熟ぶりが注目される。
「実施した」と「検討中」を合わせると、企業グループあるいは連結子会社を包含した総人員計画、連結子会社をふくむ中核企業役員の計画的育成、中核企業による連結子会社の採用・配属人事などの一元的管理について、その回答率がすべて4〜5割になる。また企業グループあるいは連結子会社による企業年金制度にかんしても、実施したあるいは検討中が3分の1にのぼる。
戻る
4. 労使関係
(労働組合の有無)
まず、労働組合が組織されているかどうか。組合が「ある」というところが78.0%、「ない」が21.9%あった。業種別にみて「ない」が多かったのはサービス業(46.1%)、卸売業や建設業でも3割を上回った。
(これからの企業内労使関係)
今後の企業内労使関係について、どのようなことが考えられるか(図3−5)。
(1)会社と社員の個別的な雇用関係の比重が高まる(雇用関係の個別化)、
(2)良好な労使関係を維持していくことが難しくなる(労使関係の悪化)、
(3)個々人の処遇や評価をめぐる苦情への対応の必要性が高まる(個別苦情処理の必要)、
(4)労働組合による経営への発言が活発化する(組合の発言の活発化)、
(5)従業員代表は監査役に加わる(労働者重役制)、
(6)労働組合の存在感が希薄化する(労働組合の希薄化)
(7)労働組合がパートなどの非正規社員の利益を守るために活動するようになる(組合による非正社員利益の代表)、
(8)管理職の組合員化が進む(管理職の組合員化)、という8つの項目について、それぞれ「大いにありうる」「ありうる」「ありえない」と考えられるかについて尋ねてみた。
第1に、「大いにありうる」という回答が多かったのは、たとえば「個別苦情処理の必要」(15.2%)、「雇用関係の個別化」(12.5%)、「労働組合の希薄化」(9.7%)などであった。
第2に、「ありうる」という回答がめだったのも、「個別苦情処理の必要」(70.9%)、「雇用関係の個別化」(55.1%)、「労働組合の希薄化」(50.3%)といったもののほか、「組合の発言の活発化」(46.1%)、「労使関係の悪化」(45.4%)、「組合による非正社員利益の代表」(42.6%)などであった。
第3に、「ありえない」という回答が多かったのは、「労働者重役制」(83.2%)と「管理職の組合員化」(64.6%)であった。
したがって、これらの結果からみるかぎり、労働組合の存在感が希薄化するのと並行して雇用関係の個別化が進み、それだけ個別苦情処理の必要が高まっていくというひとつの趨勢をみてとることができる。逆に、従業員代表が監査役に就任するとか、管理職の組合員化が進むとはみられていない。
(企業グループ労使関係のゆくえ)
すでにみたように、企業グループ人事管理の成熟が予想される。それでは、企業グループ労使関係のほうはどうか。
第1に、労働組合が組織されている場合、その組合は企業グループ労協・労連に加盟しているか。中核的組合であるかどうかは別として、「企業グループ労協・労連に加盟している」が56.2%、「グループ労協・労連はない」が35.9%であった。「グループ労協・労連があるのに加盟していない」というところは1.9%とほとんどなかった。
第2に、いかなる労使協議・団体交渉のあり方が望ましいか(図3−6)。
「企業グループ全体で労使協議するのがよい」が15.8%、「グループ全体で団体交渉するのがよい」が0.9%、「親会社の協議に子会社がオブザーバー参加するのがよい」が6.7%、「子会社の協議に親会社がオブザーバー参加するのがよい」が9.9%、「労使協議や団交はバラバラに個別に行うのがよい」が61.2%となっている。
このように、企業グループで一元化した労使協議・団体交渉を行うという意見が16.7%、親会社あるいは子会社が労使協議・団体交渉にオブザーバー参加するという意見が16.6%、したがってこれら両者を合わせると、全体の3分の1になる。しかし、労使協議・団体交渉は個別企業内で行えばよいという見方が6割を超えた。
第3に、労働協約の締結方法については、基本的な労働条件については「会社とグループ労協・労連で「包括的」労働協約を締結するのがよい」が1割強(11.9%)、「包括的労働協約は締結しないが、グループ内の話し合いは何らかの方法を工夫したほうがよい」が16.2%、「企業グループ内の労使関係はあくまで個別企業内の労使関係による労働協約によるのがよい」が7割弱(67.8%)とめだって多かった(図3−7)。
したがって、ひとことでいえば、企業グループ人事管理に比べて企業グループ労使関係は未成熟といったシナリオが浮かび上がる。
小括
(イ)労働組合は組織されていないところが、サービス業などを中心にして2割を超えた。
(ロ)これからの企業内労使関係については、労働組合の存在感が薄まるのとパラレルに雇用関係の個別化が進行し、それだけに個別苦情処理システムの整備・構築が重要な課題になるだろうという見方が多い。
(ハ)企業に組合があっても、企業グループ労協・労連が組織されている割合は6割弱にとどまる。そのこともあってか、企業グループ人事管理の成長見通しに比べて企業グループ労使関係の成熟度に欠けるといった事態が生じる可能性がある。
戻る
III まとめ
いま企業はなにを変えようとしているのか。逆に、これからも大切にしていこうと考えているものはなにか――、これまでみてきたことを改めてこうした観点から整理してみよう。
戻る
1.経営とコーポレート・ガバナンス 〜変化と持続〜
包括的な経営改革が進められ、コーポレート・ガバナンスの見直しも行われている。本調査によれば、経営およびコーポレート・ガバナンスに関わる改革として少なくとも5つの動きが注目される。
(5つの改革)
第1に、自己責任経営の明確化と企業グループとしての連結経営の強化が同時に進められていることである。
このうち、企業グループの連結経営の強化に関わる改革として、たとえば役員の少数化や会議の集約化をともなう経営トップの意思決定のスピードアップ、財務部門の強化、関連企業の整理・統合、持ち株会社の創設、企業グループ人事管理の進展などがあげられる。また、自己責任経営の明確化には「小さな本社」の構築、執行役員制度の導入、社内分社化・子会社化、取締役経験者が常任監査役になることの抑制、さらに社内分社・子会社における労働条件決定の親会社からの自立性といった内容がふくまれよう。
その逆に、社内分社化・子会社化といっても、資金調達、投資決済、役員人事などの面で社内分社のみならず子会社も親会社から必ずしも自立的でないのは、企業グループとしての連結経営の強化によるものである。
では、この自己責任経営の明確化と企業グループとしての連結経営の強化がめざしているものはなにか。その象徴的な表れといってよい社内分社化・子会社化の目的(市場の変化に敏感に対応するため、既存事業部の整理・再編のためであった)から類推すれば、要するに、企業(グループ)としての市場競争力を強めていくことであり、それによる企業(グループ)としての発展的成長が大きな経営改革の目的ということになるだろう。
第2に、自己責任経営の明確化と企業グループとしての連結経営の強化という基本設計に関連して、いま役員制度・運用および経営執行組織のありようが問い直されている。
ひとつは、役員の業績主義的少数精鋭化であり、いまひとつが経営執行組織の集権的効率化である。このうち、前者にはたとえば経営首脳の任期制、役員の定年制、執行役員制度の導入、役員抜擢人事の促進、業績査定による役員報酬格差拡大、ストックオプション制の導入といったことがあり、また後者には常務会など経営首脳会議の改廃、「小さな本社」の構築、持ち株会社の創設といった内容がふくまれる。
第3に、重視する経営指標にも注目すべき変化が生じている。全体的にはたとえば製造業、サービス業、小売業、建設業がそうであるように、売上高から経常利益へといったシフトがおきている。しかも、この経常利益重視という経営の姿勢は、機関投資家の主要な関心とよくフィットしている。
他方、金融保険業を除けば、株主資本利益率を重視する企業はまだまだ少数派にとどまる。
第4に、間接金融から直接金融への変化が生じている。最近3年間の実績に加えて、今後の取り組み予定まで視野にいれていえば――間接金融の消滅ということではないが――、たしかに銀行借り入れから社債発行へあるいは株式発行へといった流れを観察することができる。とくに社債への関心は強い。
第5に、株主とのインターフェイスという点でも多くの努力が払われている。たとえば、非効率的な株の持ち合い解消、資産の流動化、経常利益の重視、自己株の償却がその例である。
しかし同時に、安定株主の存在は重要であり、そのために機関投資家にたいする業績説明会の開催がこの数年のうちに活発化した。また一般株主向けもふくめた投資関連情報の開示も進められている。
(持続的側面)
コーポレート・ガバナンスをふくむこれらの変革がめざしているものは、すでにみたように企業(グループ)としての市場競争力の高度化であり、その成果である企業の成長と繁栄であり、ひいてはステークホールダーへの利益還元であるといってよい。ということは、上記5つの改革にもかかわらず、これからも大切にされるだろう持続的側面があるということであろう。では、なにが変わらないのか、あるいは変えないというのか。
第1に、優先的ステークホールダーという点では、従業員と株主、その後に経営者がくる。従業員重視・株主軽視ということではない。この構図はこれまでもみられたものである。
第2に、非効率的な株の持ち合い解消は進めるが、それは安定株主が要らないということではない。これからも安定株主を大切にしていこうという姿勢ははっきりしている。
では、どのようにしてか。ひとつは、投資関連情報の積極的開示のほか、たとえば機関投資家にたいする業績説明会の開催など株主広報活動の活発化を通じてである。いまひとつには、もっと根本的にすでにみたような企業の繁栄にもとづく利益還元によってである。
第3に、その機関投資家など安定株主の関心は、機関投資家アナリスト・ファンドマネージャーの関心から類推するかぎり、企業の経営戦略、主要商品の詳細情報、経常利益などに注がれている。機関投資家は経営組織や雇用慣行などの制度的改革にはほとんど関心がない。そうした改革は経営者が判断すべきことがらであるとみなしている。かれらの関心はそうした制度装置を用いて(あるいは制度改革によって)いかなる経営パフォーマンスが達成されるかにある。
子会社にたいする親会社からの発言といったことを別にすれば、株主は雇用慣行をふくめた経営制度・行動にかんして一般的に発言しないというこの基本的姿勢は、これまでも支配的なものであった。
第4に、外部取締役の導入状況(最近3年間で「実施した」が19.3%、「検討中」が14.2%)および社長の強い役員人事権についての回答結果(「あてはまる」が75.9%、「望ましい」が62.0%)から推察すると、これからも内部昇進型役員が支配的な比重を占め、その選考にあたっては依然として社長が大きな影響力を発揮していくと考えられる。
したがって、経営理念としての優先的ステークホールダー、安定株主との良好な関係、「発言しない」安定株主、内部昇進型の役員輩出パターン、社長の強い役員人事権といったことがらについては――経営組織、意思決定機関、役員人事・制度管理、経営指標、コーポレート・ガバナンス、株主広報活動などの改革にもかかわらず――、急激な変化が生じるとは考えられない。
戻る
2.雇用慣行と労使関係 〜変化と持続〜
では、雇用慣行や労使関係にかんしてはどうか。企業が変えようとしているものあるいは変わっていくとみているもの、逆に、これからも維持していこうとしているものはなにか。
(変わっていくもの)
第1に、雇用関係の個別化が進んでいる。そのため、人事考課における評価結果の本人への開示が行われ、さらにそれにともなって個々人の処遇や評価をめぐる苦情処理への対応が必要になっている。今後、この傾向に一層拍車がかかるものとみられる。
第2に、この個別化が示唆していることとして、集団的労働関係の新たな再構築といった課題、総額人件費の抑制と人材格差にもとづく年功秩序の「後退」をふくむだろう報酬格差の拡大、社内分社・子会社における労働条件の親会社からの自立化などがある。
第3に、60歳代の雇用機会にかんして、定年後の再雇用・勤務延長によってか、あるいは企業グループとしての雇用機会の確保・拡充という形でか,その機会を広げようという動きがみとめられる。
第4に、企業グループ人事管理の成熟ぶりが注目される。企業グループあるいは連結子会社をふくむ総人員計画、採用・配属など一元的人事管理、企業年金制度、さらには役員育成計画といったものがすでに一部で動き出しており、いま検討中という企業も少なくない。
第5に、企業年金制度の運用方法が改革されている。この企業年金制度に関わりがあるが、法定外福利厚生費の大幅削減の動きもみられる。
第6に、企業内労使関係については、上記の雇用関係の個別化とパラレルに労働組合の存在感が薄らいでいる。
第7に、企業グループ労使関係も構築されつつあるが、企業グループ人事管理の成長ぶりに比べてその立ち遅れがめだつ。
(変わらないもの)
こういった変化とは逆に、大きく変化していくとはみられないものがある。
第1に、終身雇用慣行が、近い将来大きく崩れるとは考えにくい。企業の基本的な考え方からして、また個別労働力銘柄別の定着率見通しからみて、さらに60歳代の雇用機会拡大にかんする企業の姿勢などから判断して、終身雇用が急激に崩壊するとはみられない。
第2に、企業年金制度の運用方法をめぐって多くの工夫が凝らされている。しかし、この制度を廃止するという企業はごく少ない。また、確定拠出型年金の導入率や今後の普及率(見通し)もけっして高くない。
第3に、労使関係については、一方で未組織セクターが拡大しながら、他方では企業グループ労使関係の形成と成熟の必要が生まれているが、なおこれからも企業別労使関係が中心的な重みをもつだろう。
したがって、終身雇用または長期安定雇用、企業別労使関係、企業年金制度といった要素は――雇用関係の個別化、年功秩序の「後退」、労働条件決定の多元化、企業グループ人事管理の成長、複線型キャリア形成の進展、企業年金制度の運用方法の改革、企業別組合の存在感の希薄化などにもかかわらず――、急激な変化を被ることになるだろうとは思われない。
戻る
3.持続と変化が示唆するもの
(株主価値最大化)
日本の経営と労働は大きな曲がり角にさしかかっている。しかし、そのすべてが変わるわけではない。
第1に、企業がその自主的判断にもとづいて選び取っている持続的なものに注目すれば、経営理念としての優先的ステークホールダー(従業員、株主、経営者)、安定株主との良好な関係、「発言しない」安定株主、内部昇進型の役員輩出パターンなどのほか、終身雇用、企業別労使関係、企業年金制度などがふくまれる。
これら持続的なものが物語っているのは、ひとことでいって、企業経営の修正日本モデルではあっても、けっして株主価値の最大化でもなければ株主資本利益率の最優先でもない。ほとんどの企業のめざしているのはそれとは基本的に違っている。
第2に、変化していく側面に注目したら別のものがみえてくるか。経営やコーポレート・ガバナンスをめぐる変革、また雇用・労使関係に関わる変化はいったい何のためか。第一義的には企業(グループ)としての市場競争力強化のためであり、それにもとづく企業の繁栄のためであり、ひいてはステークホールダーへの利益還元のためである。
このように、持続と変化いずれの側面からみても、新たに構築されつつある企業モデルがめざしているのは企業経営の修正日本モデルではあっても、株主価値の最大化ではない。
(企業のあり方の基本的視点)
したがって、企業行動の評価や格付けにあたって経営が第一義的にめざしてはいない株主価値基準によってそれを行うことは説得力に欠ける、といわなければならない。
それでは今後の企業のあり方とは何か、今までふれてきた企業自身がめざしている内容を踏まえ、今後の企業のあり方について考える際の基本的視点をあげれば次のようなものとなろう。
第1は、企業(グループ)としての市場競争力強化とステークホールダーへの利益還元に向けた経営改革への包括的取組(自己責任経営の明確化、連結経営の強化など)が積極的に行われているかという視点である。
第2は、個々の企業レベルはもとより、企業グループまでふくめた雇用機会の確保が企業経営の柱として重視されているか、また、そのための最大限の努力がなされているかという視点である。
第3は、雇用関係の個別化と企業グループとしての連結経営の強化、それにともなう集団的労働関係の「後退」と企業グループ人事管理の台頭という大きな潮流のなかで、人事評価など人事管理の基準の明確化、透明化の確保等にかんし、集団的「発言」の機会の再構築に向けた新たなルール作りに労使間で十分な協議や取組が行われているかという視点である。
これらは、いずれも今後の政策上の課題とも密接に関連するものであるといえよう。