労災保険法における「治ゆ」に関する判例
1 事案の概要
(1)原告甲は、有限会社乙に大工として雇用され、株式会社丙が元請として施工中の工事に従事していた者であるが、昭和48年9月12日、同工事現場へ通勤のため乗車していた乙のマイクロバスが後続のマイクロバスに追突され、受傷した。
(2)甲は、受傷後、直ちに病院で診療を受けたところ、「外傷性頸腕症状(休業見込日数30日)」と診断された。
(3)療養補償給付については、昭和54年8月1日から昭和56年2月23日までの間は支給されたが、それ以降については不支給となった。(昭和54年7月31日以前については、自賠責保険により治療を受けていた。)また、休業補償給付については、昭和52年1月12日から昭和56年2月23日までの間は支給されたが、それ以降については不支給となった。
2 判決要旨
(1) 昭和56年2月23日の時点においては、本件災害に係る原告の傷病による症状は固定し、同傷病に対する医学技術による治療効果を期待しえない状態になっていたと認定するのが相当である。
(2) 労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付は、労働基準法75条により、業務上の負傷等について必要な療養をする場合の補償を行うものであり、労災保険法12条の8第1項2号の休業補償給付は、労働基準法76条により業務上の負傷等の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合の補償を行うものであるところ、同法77条、労災保険法12条の8第1項3号等が負傷等のなおった後も精神、身体に障害のあることを当然の前提とし、これに対してその程度に応じ障害補償給付を行うこととしていることを考慮すれば、療養補償給付及び休業補償給付の場合の「療養」とは、負傷等による症状がすべて消退するなど、いわゆる「全治した」状態になるまでのすべての治療等を意味するものではなく、負傷等に対する医学技術による治療効果が期待できる間の治療等を意味すると解すべきである。
(1) 本件は、被災後15年、症状固定とされた後7年を経過した現在も同様の治療が継続されているだけであり、障害自体の改善の傾向は見られないことからすれば、控訴人の症状は、本質的な治療効果を期待しえない状態にあることは明らかである。患者が外来を訪れ、症状を訴えて治療を求めれば、医師としては、その症状に対応した治療を試みる義務があるから、対症療法的治療が継続していること自体は症状固定の判断に反するものではない。
(2) 労災保険法に基づく保険給付を行うか否かは、医師の診断結果を参考としつつも、同法の趣旨に則って法的に評価すべきものであって、主治医が治療の継続を必要であると診断したとしても、これに拘束される理由はなく、その他の医師の意見や鑑定の結果あるいは療養の経過等を全体的に評価して判断することが許されることはいうまでもない。
(3) 労災保険法に基づく他病院での受診命令にも正当な理由なく応じない場合に、被控訴人が、診療内容や傷病の経過を調査し、担当医師のほか労災医員等の意見を求めるのはむしろ当然の措置というべきであって、その結果に基づいて、主治医の診断に反する認定をしたとしても、これをもって差別であるとは到底言い難い。
原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。 |
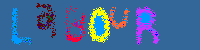 労災の治ゆ
労災の治ゆ