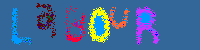 賃金制度−年俸制(2)
賃金制度−年俸制(2)■HOMEPAGE
■640/480 ■年俸制目次へ
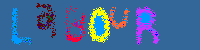 賃金制度−年俸制(2)
賃金制度−年俸制(2)
■HOMEPAGE
■640/480 ■年俸制目次へ
戻る 管理職年俸制を適用者はどう評価しているか 平成9年3月6日、日経新聞朝刊は以下のように報じている。 「管理職の年俸制不満が募ります」 「肯定派」2割減 評価に疑問抱く(労務行政研が調査) 年俸制についてサラリーマンの不満が高まっていることが、民間の調査機関、労務行政 研究所(猪俣靖理事長)が5日まとめた「適用管理職のホンネ調査」でわかった。 年俸肯定派が前回調査の6割から4割に減っているほか、「どちらとも言えない」とす る”あいまい派”も4割近くに達した。同研究所では「不況下でのコスト抑制策と考え ている人が多く、中高年ホワイトカラーの活性化にとって有効かどうかを検証するには まだ時間がかかる」と分析している。 <本文記事は以下のようなものである> ●調査は昨年11月から今年1月、年俸制を導入している主要28社のうち、実際に制 度を適用されている管理職(課長職相当以上)を対象に実施。283人から回答があ った。 ●「年俸制を受けてよかった」とする人は38.5%で、94年の前回調査の59.6 %に比べ21.1ポイント減った。逆に「どちらとも言えない」は39.2%、「悪 かった」は15.2%とそれぞれ5.1ポイント、8.9ポイント増えた。 ●年俸制適用後の意識の変化(複数回答)では、「経営に対する参画意識が高まった」 は28.6%で、前回調査の58.1%から激減。 「人間関係がドライになった」(24.4%)は10ポイント増えた。 ●適用でよくなった点(複数回答)は「仕事の目標が明確になった」(59.7%)「 部下の指導、仕事のやり方を絶えず考えるようになった」(33.9%)「チャレン ジ意欲が強まった」(29.0%)の順。 ●悪くなった点は、「業績が年俸に結びつき、年俸ダウンが心配」が38.5%で最も 多く。次いで「短期的業績を追うようになった」(36.4%)「定期昇給的な賃金 保障がなくなった」(34.3%) (以下、労務行政研究所による調査から)
年俸制度適用後、よくなった点・悪くなった点
| よくなった点 | % | 悪くなった点 | % |
| 仕事の目標が明確になった | 59.7 | 会社(部門)業績が年俸に結びつきダウンが心配 | 38.5 |
| 部下の指導、仕事のやり方をを絶えず考える | 33.9 | 短期的な業績のみを追う | 36.4 |
| チャレンジ意欲が強まった | 29.0 | 定期昇給的な賃金保障がなくなった | 34.3 |
| 年収が明らかなので生活設計が立てやすい | 23.3 | 査定が厳しくなった | 20.5 |
| 経営参画意識が強まった | 23.3 | 人間関係がドライになった | 17.7 |
| 責任感が増した | 21.6 | 忠誠心が弱くなった | 13.1 |
| やればやっただけ評価される | 20.1 | 責任だけが重くなった | 11.3 |
| 面接等を通じ、上司とのコミニュケーションの機会が増えた | 16.3 | 仕事がきつくなった | 9.5 |
| 自己評価により年俸額の申告ができる | 11.0 | 賞与時に賞与がなく収入感がない | 5.7 |
| 生産性が高まった | 9.2 |
| 評価基準が不明確 | 52.7 |
| 評価にバラツキがあり公平性に欠ける | 36.4 |
| 人件費削減の色彩が強い | 32.9 |
| 個人業績があまり反映されていない | 29.7 |
| 面接・話し合いの機会が少ない | 27.2 |
| 従来の賃金制度と大差がない | 26.1 |
| ドライな年俸決定ができない | 18.4 |
| 年俸額が低く、インセンティブにならない | 15.5 |
| 査定幅が小さい | 15.2 |
| 年俸への反映度が強すぎる | 2.1 |
| その他 | 3.5 |
戻る デイエフアイ西友事件(東京地裁平成9年1月24日決定) 決定要旨 ・期間の定めのない雇用契約における年俸制は、固有の意味での年俸ではない ・配転は使用者の裁量で可能だが、配転と賃金とは別個の問題であり ・配転による職種変更は年俸額を一方的に減額するための法的根拠とはならない。 事件概要 社長のスペシャル・アシスタントとして年俸784万余で採用された女性社員が、その後 商品部のバイヤーに配置転換になったものの、勤務成績不良を理由にバイヤーアシスタン トに降格され、賃金も大幅にダウンされたため、不当として仮処分の申立に至ったもの。 決定文のあらまし 第三 当裁判所の判断 一(雇用契約の成立について) 1 債務者が債権者を平成7年に雇用したこと、雇用条件は、採用後3ケ月間を試用期間 とし、当初の賃金額を年俸730万円とするものであったこと、試用期間経過後の時点に おける債権者の賃金額が年俸784万7500円であったことについては、いずれも当事 者間に争いがない。 2 なお、契約の成立時期については、債務者から債権者宛の平成7年11月1日付書簡 によれば、同書簡に「貴女が我社へ入社された3ケ月後である1995年8月7日」と明 記されているとおり、平成7年5月8日であることが疎明される。この点に関して、債務 者が雇用契約締結日として主張する同年4月19日は、雇用契約の締結に至るまでの交渉 過程においてなされた雇用条件の申込日こ過ぎず、その時点では、契約締結に至ってはい なかったものと解され、したがって、仮に同年4月19日に何らかの合意が成立していた としても、・・・雇用契約の予約的なものであったと解すべきである。 そして、右雇用契約に基づき、債権者は、同年5月8日から債務者代表者のスペシャル・ アシスタントとして就労を開始したが、同年5月23日付債務者から債権者宛の書簡によ れば、債務者は、契約内容である賃金額に関する債権者の要望を受け入れて、同月23日 、賃金額を当初約定金額である年俸700万円から年俸730万円へ増額することを約し たことが疎明される。 3 したがって、債権者と債務者間の本件雇用契約の締結日及び就労開始日は、平成7年 5月8日であり、同日から起算して3ケ月の試用期間経過後の賃金額は、年俸784万7 500円(年俸額を12ケ月で除した月割額は65万3958円)である。 4 以下、右疎明事実を前提に、本件について判断する。 二(配転に伴う賃金減額の正当性について) 1 一般に、労働者の賃金額は、当初の労働契約及びその後の昇給の合意等の契約の拘束 力によって、使用者・債務者とも相互に拘束されるのであるから、労働者の同意がある場 合、懲戒処分として減給処分がなされる場合その他特段の事情がない限り、使用者におい て一方的に賃金額を減額することは許されない。 2 ところで、本件において、債務者が一方的措置として債権者の賃金額を減額したこと については、当事者間に争いがない。この賃金の一方的な減額を正当化する根拠として、 債務者は、経営者としての裁量権の行使として賃金額減額をすることができる旨を主張す る。しかしながら、経営者としての裁量権のみでは、一方的な賃金減額の法的根拠となら ない。なお、本件における減額が勤務成績不良による懲戒処分としての減額の場合である とするならば、就業規則の定めその他の懲戒処分の根拠を主張・疎明する必要があるが、 このような主張・疎明はない。 3 他方、債務者は、債権者が業務成績不良であるため、債権者に対し、当初の契約内容 とは異なる職種への配転を命じ、この配転に伴って、配転後の職種の他の従業員と同等の 賃金額に減額したものである旨を主張する。たしかに、配転については、原則として、経 営者の裁量権が尊重されるべきであり、労働者は、具体的な職務内容を求めることのでき る具体的な請求権を有しないと解するべきである。 しかしながら、配転と賃金とは別個の問題であって、法的には相互に関連しておらず、 労働者が使用者からの配転命令に従わなくてはならないということが直ちに賃金減額処分 に服しなければならないということを意味するものではない。使用者は、より低額な賃金 が相当であるような職種への配転を命じた場合であっても、特段の事情のない限り、賃金 については従前のままとすべき契約上の義務を負っているのである。 したがって、本件においても、債務者から債権者に対する配転命令があったということ も契約上の賃金を一方的に減額するための法的根拠とはならない。 4 なお、本件雇用契約が期間を定めない労働契約であることについては、当事者間に争 いがないから、本件雇用契約における賃金の定め方もまた、固有の意味での年俸ではない 。 すなわち、固有の意味での年俸は、契約期間を1年とする雇用契約における賃金であっ て、その金額に関する契約上の拘束力も契約期間である1年間に限定される。したがって 、固有の意味における年俸にあっては、1年間の契約期間が経過した後、年俸額も含めて 従前通りに契約更新をする旨の合意が存在しない限り、前年度の年俸額がそのまま次年度 の年俸額となるわけではなく、仮に雇用することのみについて契約更新をすることの合意 が成立し、年俸額については合意が成立しないというような事案があるとすれば、そのよ うな年俸額に関する合意未了の労働者は、賃金債権につき契約上の何らの発生原因を有し ないことになり、たかだか当該年度において当該契約当事者双方に対して適用のある最低 賃金の額の限度内での賃金債権を有するに過ぎないことになるであろう。 右のようにかかる固有の年俸制による労働契約にあっては、各契約年度の賃金債権は、 使用者と労働者との間の合意によってのみ形成されることになるから、労働者の前年度に おける勤務実績や当年度における職務内容等の諸要素によって、事実上、前年度よりも年 俸額が減少する結果となることもあり得ることであり、それが当事者間の合意に基づくも のである限り、年俸額の減少は、適法・有効である。 しかしながら、前記のとおり、本件雇用契約は、期間の定めのない労働契約であり、右 のような意味での固有の年俸制による労働契約ではないのであるから、この意味において も、本件において、使用者たる債務者から労働者たる債権者に対してした一方的な賃金の 減額措置は、無効である。 5 以上を要するに、債権者は、その主張のとおりの被保全権利を有しているのであり、 債務者は、債権者に対して、平成8年6月13日以降においても、年額784万7500 円の割合による賃金を支払うべき契約上の義務を負っているのである。 (以下略) 戻る 社員の評価に悩む−年俸制導入企業の4割 士気低下の危険性指摘 との見出しで日経新聞(H10.2.28朝刊)が社会生産性本部調べとして、要旨、次のように報道している。 年俸制を導入した企業の4割が社員の評価方法について悩みを抱えていることが、社会 生産性本部(亀井正夫会長)がまとめた「日本的人事制度の変容調査」でわかった。同本 部では「成果主義人事制度を導入しても評価が納得いかないものであれば働く側の志気は かえって低下してしまう危険がある」と分析している。 ○調査はH9.11、上場企業2,246社の人事労務担当役員・部長を対象に実施、回答380社(16.9%) ○年俸制導入企業は、18.7%。(96年1月調査の9.8%からほぼ倍増) ○導入企業に評価の現状を聞いたところ、 ・ほぼうまくいっており、現在特に問題がない 18.3% ・あまりうまくいっておらず、早急に改善する必要がある 2.8% ・特に問題は起きていないが、改善の必要は大いにある 38.0% ・まずまずうまくいっているが、多少の改善が必要である 36.6% このように、約4割の企業が課題を持っており、7割以上の企業が改善の必要を感じて いる。 ○問題点として、 ・「評価者間で基準の統一が難しい」 ・仕事の質の異なる人たちを適切に評価することが難しい」 を挙げる企業がそれぞれ、65.5%、60.0%あった。 ○成果主義賃金と評価制度との関係では、「評価制度が不十分なうちは、早急に成果主義 を導入すべきでないが51.6%と過半数。「不十分でも導入することが不可欠だ」の36.0% を上回った。