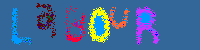 「新・労働基準法」の実務解説
「新・労働基準法」の実務解説5.一年単位の変形労働時間制
■HOMEPAGE ■640/480 ■新労基法と実務へ
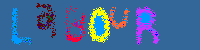 「新・労働基準法」の実務解説
「新・労働基準法」の実務解説
5.一年単位の変形労働時間制
■HOMEPAGE ■640/480 ■新労基法と実務へ
| 1年単位の変形労働時間制 | 1 | 予備知識 | 4 | 1年単位の変形労働時間制の導入要件 |
| 2 | H10年改正のポイント | 5 | Q&Aでおさらい | |
| 3 | 労働日数・労働時間の制限は新旧どう変わったか(早見表) | 6 | 施行通達確認 |
| H10年改正のポイント |
| 1. | 対象期間の全部を通じて使用される労働者以外の中途採用者、期間途中で退職が予定されている労働者についても1年単位の変形労働時間制の対象にできることとなった。この場合の中途採用者、中途退職者に対する時間の清算取扱いとして、対象期間に労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えた時間について、割増賃金の支払義務を課すこととなった。(これによって、同 一事業場で複数の労働時間制が併存する不 都合を回避できることとなる。) |
| 2. | 対象期間を1ヵ月以上(従前は3ヵ月以上だった)の期間に区分して労働日、労働時間を特定できるようになった。この場合、区分期間の各初日から30日前までに、事業場の過半数組合又は代表者の同意を得て、各期間の労働日と労働時間を定めなければならない。 |
| 3. | 対象期間の最長労働日数及び最長所定労働時間が法定化された。 最長労働日数:1年当たり280日(一定の場合これより少なくなることあり。) 最長所定労働時間:1日10時間、1週52時間(但し、対象期間が3ヵ月を超える場合は、「週48時間を超える週が連続して3以下で、かつ3ヵ月に3以下」になるようにすることが必要。 |
| 4. | 対象期間中の連続労働日数の制限が設けられた。 連続労働日数:6日(特定期間中は週1日の休日が確保できる日数) |
| 5. | 育児、介護その他特別の配慮を要する者については、その時間が確保できるよう配慮すること。 |
| 6. | 対象期間が3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制では、36協定の延長限度時間が一般より短い設定となったこと。 |
|
制限事項 |
改正前 |
改正後 |
|
| 1. | 労働日数 | 制限なし | <対象期間が3ヶ月を超える場合> 1年当たり280日。1年未満の限度日数の計算は 280×(対象期間の日数÷365)で計算する。 |
| 2. | 1日及び1週間の労働時間 | <対象期間が3ヶ月以内の場合> 1日10時間、1週間52時間 <対象期間が3ヶ月を超える場合> 1日9時間、1週間48時間 |
対象期間に関係なく一律に 1日10時間、1週間52時間。 但し、 <対象期間が3ヶ月を超える場合> 48時間超えの週は連続3以下、かつ、3ヶ月毎に区分した各期間において48時間超えの週が3以下であること。 |
| 3. | 対象期間における連続労働日数 | 1週間に1日の休日が確保できる日数 | 6日 |
| 4. | 特定期間における連続労働日数 | 制限なし | 1週間に1日の休日が確保できる日数 |
| 5. | 育児を行う者等に対する配慮 | 配慮するよう務めなければならない | 配慮しなければならない |
| 1年単位の変形労働時間制の導入要件(今回の改正点は赤字で表示) |
| 1. | 対象者の範囲 | →(改正)対象労働者の範囲の限定はなくなった。 中途採用者、中途退職者にも採用可能に |
| 2. | 対象期間と起算日 | 対象期間を平均し1週間当たり労働時間が40時間を超えない範囲で1年以内。 |
| 3. | 特定期間 | 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)を設定する場合は、その定め。 |
| 4. | 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間 | この部分は、以下の方法により特定することができる。 <期間中の労働日、労働時間の特定> ○期間を区分しない場合 ○期間を複数に区分する場合 1ヵ月以上の期間で区分が可能。この際、労使協定に定めを要する事項は次のとおりです。 1. 最初の期間における労働日 2. イの労働日ごとの労働時間 3. 最初の期間を除く各期間における労働日数 4. 最初の期間を除く各期間における総労働時間 (最初の期間とは、区分された各期間のうち例えば1年間期間の初日の属する期間をいう。) |
| 5. | 有効期間 |
| Q&Aでおさらい |