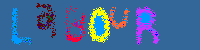 福利厚生制度のいま
福利厚生制度のいまGO HOMEPAGE
GO 640/480
福利厚生制度の総目次へ
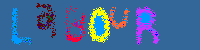 福利厚生制度のいま
福利厚生制度のいま
GO HOMEPAGE
GO 640/480
福利厚生制度の総目次へ
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3 勤労者拠出年金制度案(財形年金貯蓄制度再編の方向)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
財形年金貯蓄制度を基本として、わが国における勤労者拠出型年金制度のあり方を検討するにあたっては、前述の検討比較表(図表4)から、現行の財形年金貯蓄制度の以下の点を中心に改訂を考える必要がある。
A.勤労者拠出に対する税制上の支援が、厚生年金基金は所得控除(社会保険料控除)であるのに対し、財形年金貯蓄制度は課税後給与からの拠出(利子非課税)であること
B.事業主の任意拠出はあるものの、制約(上限10万円/年・人、7年)があること
C.取り扱う金融機関等はほとんど自由であるが、預替えができない等制約も多いこと
そこで、財形年金貯蓄制度を、より有効な勤労者拠出型年金制度として機能させていくための制度再編案について検討する(図表7=省略)。
−−−−−−−−−−−−
(1)案1:個人契約型
−−−−−−−−−−−−
A.概 要
財形年金貯蓄制度が、勤労者の自助努力型年金として多くの企業に普及していることを踏まえ、その水準面での拡充を図るとともに、事業主拠出の方法について、抜本的な改善を図る。
すなわち、元本550万円(保険等は払込合計額385万円)の利子非課税については、自助努力支援の重要性に鑑み、他の企業年金等の勤労者拠出に関する税制上の取扱いに合わせ、一定額までの所得控除を認めるものとする。これにより、勤労者の拠出に対するインセンティブが、より高まることが期待される。また、これまで財形貯蓄全般に適用されていた事業主の財形給付金・基金制度については、財形年金貯蓄のみに特化する形に改正する。それに伴い、7年毎に給付するという従来の方式を、勤労者の退職時に一括して給付する形に改めるとともに、年間一人あたり10万円という給付金の限度枠を拡大する。このように、勤労者、事業主双方について、拠出のあり方を見直すことによって、勤労者が確保できる老後資金の拡充を図っていくこととする。
給付形態は、原則として年金とするが、全部又は一部について一時金受取りを認めることとする。なお、給付についても、他の企業年金等の給付等の税制上の取扱いに合わせ、勤労者が年金を受給する場合は雑所得(公的年金等控除を適用)として、一時金として受給する場合は退職所得として課税することとする(図表8=省略)。
(注)この図の「個人勘定」は、個人別に拠出の元利合計額(残高)が実際に積み立てられ、一定の制限はあるものの途中で引き出し得るものである。しかし、スウェーデンやイタリアの公的年金のように、会計上個人別に拠出の残高が管理され、一定の想定利率のもとに年金受給額が決定されるものの、実際には積立金が存在せず(一部分存在する場合はある)、帳簿上だけで、途中で引き出し得ないような「個人勘定」の例もある。
B.勤労者拠出
a 契約
現行どおり、勤労者が金融機関等と契約を締結し、事業主による給付天引及び払込代行により、定期的に金融機関等への預入(拠出)を行う。
b 拠出額、税制上の取扱い
現行は課税後給与から給与天引で拠出し、元本550万円(保険等は払込合計額385万円)までに対して利子非課税という取扱いであるが、自助努力型の年金制度が重要となる中で、公的年金を補完し、老後の所得を保障するという財形年金貯蓄の機能に鑑み、財形年金貯蓄への本人の預入についても、社会保険料控除が認められている国民年金基金の掛金や厚生年金基金の加算部分の加入員掛金と、税制上同様の取扱いとし、年間拠出額について一定限度額までの所得控除(社会保険料控除に準ずる所得控除)を認める。
C.事業主拠出
a 契約
事業主が現行より支援できるよう、財形給付金制度を改善する。枠組みとしては、現行の財形給付金制度と同様に、金融機関等と事業主が、その雇用する勤労者を受益者とする契約を行い、金融機関等への拠出を行うこととする。
b 財形年金制度に特化した事業主拠出制度
現行の財形給付金制度では、給付金は、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄、一般財形貯蓄のいずれの財形貯蓄を行っている勤労者に対しても支払うことができるが、本案では、財形年金制度を行う勤労者のみに給付金を支払うための事業主拠出制度に改めることとする。
c 拠出額、拠出時期、拠出段階の税制上の取扱い
現行は、給付金の上限として勤労者一人あたり年間10万円という枠があるが、勤労者の拠出額以内まで制限を緩和する。現行の給付金と同様に、毎年、毎月等定期的に契約機関に拠出し、勤労者の個人契約・勘定とは別契約・別勘定で管理することとする。事業主拠出分については、現行どおり損金算入を認める。
d 勤労者への給付
現行の制度では、一定期間(原則として7年)経過後に所定期間内に払込みが行われた拠出金の元利合計が勤労者に支払われ、そのときに一時所得として勤労者に対する課税が行われている。本案では、「一定期間」の枠を外し、勤労者の退職後に給付するものとする。
e 勤労者への受給権(Vesting、企業等に没収されることはなく、退職等一定の要件を満たせば受給することができる権利。以下同じ)の付与
現行の制度では、実際に勤労者に給付されるのは7年毎だが、その前に退職した場合などについても、事業主拠出分を事業主が没収することはなく、勤労者に給付がなされる。したがって、現行の制度においては、事業主が給付金を拠出した段階で勤労者に受給権が付与されている。本案では、事業主の拠出をより容易にするために多様な選択肢を用意し、受給権を、事業主の拠出と同時に勤労者に100%付与するか、拠出から一定期間経過後に付与するかといった点については、基本的に労使の合意によって決定することとする。 ただし、一定期間経過後とする場合でも、受給権付与の最低限のルール化が必要であろう。
f 財形基金制度
現行の制度と同様に、事業主が財形基金に拠出し、財形基金が財形貯蓄取扱機関(財形給付金制度における機関に加えて、銀行、証券等)に運用させることができるものとする。この場合も事業主拠出分及びその運用益を、7年毎でなく、退職後に勤労者に給付することとする。
D.運用選択
a 勤労者拠出分
現行どおり、勤労者拠出分に関しては、勤労者自身が、事業主が提示した範囲内で財形年金商品を選択し、個別に契約することにより、運用選択を行うものとする。ただし、現行の財形年金貯蓄制度では、原則として一度契約した財形年金商品や金融機関等を中途で変更することはできないが、本案では中途での変更(預替え)を認めることとする。
b 事業主拠出分
現行どおり、事業主拠出分については、事業主又は財形基金が運用先を選択する。
E.給付
a 給付の原資
勤労者拠出分、事業主拠出分及びこれらの運用益が給付の原資となる。なお、事業主又は財形基金、及び勤労者が契約したそれぞれの金融機関等から給付を受けることとなる。
b 給付時期
現行の制度では、年金の支払いは勤労者が60歳に達した日以後かつ定期の積立が最後に行われる日から5年以内に開始となっている。本案においても、制度の趣旨から、支払い開始の下限年齢は60歳と設定するのが妥当である。支払い開始の上限年齢については、できるだけ個々の勤労者のニーズに合わせて弾力的に選択できる形が望ましい。
c 給付形態
原則として年金として給付する。ただし、年金原資の全部又は一部について、一時金受取りも認めることとする。
厚生年金基金、適格退職年金と同様、年金として受給する場合には、雑所得(公的年金等控除を適用する)として課税し、一時金として受け取る場合には退職所得として課税を行うものとする。
d 中途払出し
税制の優遇措置を講ずるので、原則として中途払出しは認めない。ただし、現行制度同様、給付年齢(60歳)に達する前の中途払出しについては、本人の死亡、重度障害及びその他やむを得ない理由(災害・疾病等)の払出しに限って認める。それ以外の事由による払出しの場合には、何らかの課税措置を設ける必要がある。
F.転職時等の取扱い
現行どおり、転職等の際に、転職先に財形年金制度がある場合には、転職先の制度に移し替えることができることとする。また、転職先に財形年金制度がない場合についても、別途の対応を設ける。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(2)案2:企業・基金とりまとめ契約型
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A.概 要
現行の財形年金貯蓄では、勤労者それぞれが金融機関等と契約する形をとっているが、案2では、事業主又は財形基金が、運用方法の選択肢毎に個々の勤労者の拠出をとりまとめ、金融機関等と勤労者拠出の運用等に関する契約を行うこととする(勤労者は金融機関等と直接に契約はしない)。勤労者の拠出をとりまとめて一定規模の運用資金を確保することによって、運用の幅が広がり、運用コストが軽減される可能性が、今後高まってくると考えられる。さらに、案2では、事業主拠出分について、別建てでなく、勤労者拠出と合わせて運用することも認めることとする。
財形年金貯蓄の拡充(勤労者拠出に所得控除を認めることや給付時に退職金税制を適用すること等)、給付金を財形年金に特化する等その他の点については、案1と同様とする(図表9=省略)。
B.勤労者拠出
a 契約
勤労者は、事業主の提供する財形年金制度への加入を事業主に申し込む形をとり、金融機関等との契約は事業主が行う。つまり、勤労者は直接に金融機関等と直接契約はしない。
b 拠出額、税制上の取扱い
案1と同様、拠出は、事業主による給与天引・払込代行により定期的に行い、勤労者拠出分は勤労者の個人勘定に積み立てる。年金拠出額について一定限度額までの所得控除(社会保険料控除に準ずる所得控除)を認める。
C.事業主拠出
a 契約
案1と同様に、事業主が金融機関等と契約し、勤労者拠出分の上乗せとして拠出するか、事業主拠出分を、勤労者拠出分と合わせて個人勘定に積み立てるか、勤労者拠出とは別建てで個人別に積み立てるかについては、労使の選択によるものとする。
b 財形年金制度に特化した事業主拠出制度
案1と同様に、財形年金制度に限定した事業主拠出制度の仕組みを作ることとする。
c 拠出額、拠出時柵、拠出段階の税制上の取扱い
案1と同様に、
・財形年金制度は、勤労者拠出を基本とする制度であることから、事業主拠出額(給付金)の上限は、勤労者本人の拠出額以内とする。
・拠出は、毎年、毎月等定期的に行うこととする。
・事業主拠出分は損金算入を認める。
d 勤労者への給付
案1と同様に、勤労者の退職後に給付する。
e 勤労者への受給権の付与
案1と同様に、受給権の付与については労使の合意によって決定する。ただし、事業主拠出と勤労者拠出をまとめて運用する場合は、拠出と同時に勤労者に受給権を付与することとなろう(事業主拠出時に勤労者に受給権を付与しないとすれば、個人勘定を、勤労者拠出分と事業主拠出分とで分離して管理する必要がでてくる)。
f 財形基金制度
事業主が勤労者拠出分も含めて財形基金に拠出し、財形基金が財形貯蓄取扱機関(財形給付金制度における機関に加えて、銀行、証券等)に趣用させることができるものとする。この場合も、事業主拠出分、勤労者拠出分及びこれらの運用益を、退職後に勤労者に給付することとする。
D.運用選択
a 勤労者拠出分
勤労者拠出分に関しては、勤労者自身が、事業主が契約する金融機関等の提供する運用方法の中から選択する。事業主は、一定期間毎に金融機関等との間で、選択肢として勤労者に提示する運用方法の見直しをすることとする。事業主の提示する選択肢の範囲内で、勤労者が運用方法の変更をすることもできるようにする。
b 事業主拠出分
事業主拠出分を、勤労者拠出分と一本化して運用する場合には、勤労者が選んだ運用方法によって行われることとなる。別建てで運用する場合には、勤労者、事業主又は財形基金が別途運用を選択する。
c 運用リスク
事業主又は財形基金が金融機関等との契約の当事者となるので、労使の協議により、運用リスクについて、事業主が一定の補填を行うことも可能とする。
E.給 付
案1と同様に、
・勤労者拠出分と事業主拠出分、及びこれらの運用益が給付の原資となる。
・給付形態は、原則として年金とする。ただし、一部又は全部について一時金受取りも認める。
・支払い開始の下限年齢は60歳とする。支払い開始年齢の上限年齢については、できるだけ個々の勤労者のニーズに合わせて弾力的に選択できる形が望ましい。
・原則として年金(雑所得(公的年金等控除あり)課税)として給付するが、一時金受取り(退職所得課税)も認める。
・給付年齢(60歳)に達する前の中途払出しは、やむを得ない理由(災害・疾病等)の払出しに限定し、それ以外は、何らかの課税措置を設ける。
F.転職時等の取扱い
案1と同様に、転職等の際に、転職先に財形年金制度がある場合には、転職先の制度に移替えができることとする他、転職先に財形年金制度がない場合についても、別途の対応を設ける。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(3)参考案:退礎金の即時受取・据置選択型
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
案1及び案2については、勤労者拠出を制度の基本にした勤労者拠出型年金制度であるが、最近一部で検討が始まっている退職金支払い形態の多様化に着目して検討した改正案について、以下言及する。
退職金原資について勤労者が主体的に受取り方法を選択することは、現在あまり認められていない。しかしながら、退職金が賃金後払いであるという考え方に着目した時、退職金原資の一部について、在職時に即時に受け取るか、退職時まで受取りを据え置くかという選択を勤労者に認めることは、十分検討に値するものであるといえる。
事業主サイドにとっても、人材の確保及び勤労者の多様なニーズに応える観点からも、退職金の一部について、在職時より勤労者にその受取り方法の選択権を与えることは、十分意義あるものと考えられる。そこで、勤労者が退職金原資の一部の受取りを退職時まで据え置くことを選択した部分を社外に積み立てる受け皿となる制度を、参考案として提案することとする(図表10=省略)。
参考案においては、勤労者が、事業主からの一定の給付額(給付額の財源は退職金原資の一部)を給与として現行給与に上乗せして受け取るか、又は退職金として据え置いて受け取るかを選択する。勤労者が退職金として受け取ることを選択した部分(以下、勤労者据置選択部分という)については、事業主拠出として、事業主が、個人勘定別に勤労者の退職時まで外部積立を行う。
案2の企業・基金取りまとめ契約型とほぼ同じ形態であるが、制度の基本となる拠出は勤労者拠出に代わり、前述した勤労者据置選択部分(事業主拠出)とする。
事業主は、勤労者据置選択部分に加えて、任意に上乗せ拠出をすることができる。事業主拠出分(勤労者据置選択部分を含む)については、拠出時の損金算入を認める。勤労者据置選択部分について、その時点で勤労者にとって自由に処分できる所得とはみなさず、退職による給付時まで課税を繰り延べる。
なお、事業主拠出(勤労者据置選択部分を含む)を退職金として積み立てると考えれば、拠出の上限の設定は必要ないと考えられる。また、退職金の性格に鑑み、事業主拠出(勤労者据置選択部分を含む)の退職より前の中途払出しは認めないこととする。
案1及び案2と同様に、給付形態は年金を原則とするが、勤労者の疾病、災害等やむを得ない事確に対処できるよう、一時金受取りも認める。事業主拠出分(勤労者据置選択部分を含む)は、勤労者の退職後に給付し、年金の場合は雑所得(公的年金等控除の適用あり)として、一時金の場合は退職所得として課税する。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(4)勤労者拠出型年金制度実についての検討事項
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A.勤労者拠出分の所得控除の必要性
案1及び案2では、勤労者拠出分についての拠出段階での所得控除を提案している。これは、今後高齢期の所得保障のための自助努力型年金の重要性が増大することを踏まえた提案である。
これまで、個人の拠出による年金積立に関する所得控除としては、厚生年金基金及び国民年金基金における掛金(国民年金基金については一人あたり月6万8000円が上限)の社会保険料控除及び個人年金等の個人年金保険料控除(年あたり最高5万円)又は生命保険料控除(年あたり最高5万円)などがある。
公的な社会保険料については、制度加入が強制力を持っているために、公租公課の負担に準じて社会保険料控除が認められているが、前述のように、厚生年金基金の加入員掛金についても限度額なしの社会保険料控除が認められているなどの現状があり、強制加入であることが必ずしも社会保険料控除の必要要件ではなくなっている。
したがって、年金の要件として、積立期間、給付期間、給付形態等を制限した上で、要件を満たす制度において勤労者が拠出する一定の金額までは所得控除を認めていくという方向が検討されるべきであろう。
B.所得控除の上限の設定
社会保険料控除に準じた形での所得控除を実施する場合に、その上限設定が問題となる。
上限設定にあたっての一つの方法としては、公的年金や退職金の水準の動向を踏まえ、高齢期の生活を送るために必要な水準と公的年金、退職金の受給により高齢期に受け取る所得との差額を退職時点で積み立てておくために、必要な年金額をべースにして算出するということが考えられる。
もうーつの方法としては、現在社会保険料控除が認められている厚生年金基金あるいは国民年金基金の加入員掛金の水準を参考にしつつ、公的年金及び私的年金の掛金を合算して一定金額までの所得控除を認めていくという方向が考えられる。
勤労者の資産状況、家族構成等により、高齢期における勤労者の資金のニーズが多様であることから、一律に必要な年金額を決めることは困難であると考えられる。従って、前者のように、高齢期の生活を送るために必要な水準をもとに、社会保険料控除に準じた所得控除の上限を求める方式は難しい。むしろ、後者の方法により、検討することが適当であると考えられる。
C.積立金に対する税制上の取扱い(特別法人税)の検討
事業主拠出分(参考案の勤労者据置選択部分を含む)及び運用益について、従来の考え方に立てば特別法人税が課されると考えられる。
特別法人税に関しては、経営者団体を中心にして撤廃の提言がなされている。例えば、日本経営者団体連盟「企業年金制度に関する緊急提言」(平成8年)においては、「企業年金の重要性が一層大きくなる中で、(中略)企業年金の役割が十分果たし得るよう税制面の改善整備を行うことが不可欠である。」として特別法人税の撤廃を主張している。また、経済団体連合会「財政構造改革ビジョン」平成9年)において、企業年金制度の改正事項として特別法人税の撤廃をあげている。
このような状況下、今後特別法人税のあり方についての検討が期待されるところであるが、その際は、企業年金のみならず、自助努力型年金である財形年金貯蓄制度における特別法人税課税についても、同様の取扱いがなされるべきである。
D.運用のあり方の検討
運用のあり方を検討するにあたっては、老後のための財源であるという拠出の位置づけを踏まえ、特に個人の運用リスクについて、十分留意する必要があると考えられる。勤労者による運用方法の選択の前提として、勤労者への情報開示、教育の徹底、事業主や金融機関等が負う受託者責任の内容の明確化、運用方法に関する一定のガイドライン設定等について、別途検討を行う必要があろう。
一定規模の運用資金を確保することが可能とみられる案2や参考案においては、事業主等が、投資顧問会社等との契約により、独自の運用を行うことも一つの方法であると考えられる。ただし、勤労者拠出を含む老後のための財源について、このような運用を行う場合には、事業主と個人のいずれが運用のりスクを負うことになるのか、再度検討する必要がでてくるだろう。
また、401(k)プランでは、事業主拠出の一つの形態として、自社株による上乗せ拠出が認められており、最近では、ストックオプション(予め決められた価格で自社株を買う権利付与)による上乗せ拠出の事例もみられている。
わが国においても、商法改正により、平成9年よりストックオプションが解禁される中で、自社株やストックオプションを、事業主拠出の一つの形態として認めるか否かという点についても、将来的に検討していく必要があると考えられる。
E.転機時等の取扱い
転職時等の対応として、本案では、
・転職先に財形年金制度がない場合や給付年齢に達する前に退職する場合には、それまでの積立額を、ある一定の要件を満たした場合に限り、転職(離職)元の事業所の財形年金制度の勘定に残しておく仕組みを作ること
・連合会のような機関(事業主にかわって、勤労者が拠出した資金の管理等を行う機関)を新設し、そこに移管することができる仕組みを作ること
・現在一般財形貯蓄について認められている特例自己積立制度(前号図表6)を大幅に拡充し、財形年金制度に適用すること
について検討する必要があろう。
また、転職時等においても、勤労者個人と金融機関等との契約を継続し(案2の場合は、事業主と金融機関の契約を、勤労者個人と金融機関等との契約に切り替え)、引き続き個人勘定への積立を行うことができるような仕組みの検討も必要と考えられる。
−−−−−
まとめ
−−−−−
少子・高齢化等に伴い、公的年金制度や退職金制度について、これまでのような給付水準の維持を期待することは難しくなりつつある。加えて、高齢期の社会保険料等の負担増が見込まれる中、高齢期の経済生活の安定を図るための在職中からの自助努力が、今後より重要性を増してくると考えられる。
また、勤労者のライフ・スタイルの多様化に伴い、それぞれのニーズに応じた老後における準備が可能な制度の整備が求められている。一方で、退職金を給与として受け取ることを勤労者が選択できる制度の導入等、勤労者のニーズへの柔軟な対応を模索している企業もみられ、このような労使の多様な選択に適合するシステムを受け皿として整備する必要性も高まっている。さらに、今後、産業構造や勤労者のライフ・スタイルの変化等に伴う労働移動の増加が予想される中、中途退職者が老後のための十分な準備を行うことを支援するシステムの構築が求められている。
以上のような変化に対応する上で、自助努力による高齢期の所得準備としての「勤労者拠出型年金制度」の整備が求められている。すでに、アメリカでは、勤労者拠出型年金制度として、いわゆる「401(k)プラン」が普及している。わが国において勤労者拠出型年金制度を検討する上で、401(k)プランの仕組みは非常に参考になる。この401(k)プランの優れた点を参考にしつつ、より有効な勤労者拠出型年金制度を検討するにあたり、現行制度の中でも401(k)プランの特徴を多く備える財形年金貯蓄制度に注目して、その再編の方向について検討してきた。検討の結果、本研究では次の3つの案を提案した。
案1は、勤労者個人と金融機関等が契約を行い、勤労者拠出部分を拠出段階で所得控除扱いとし、給付時まで課税を繰り延べるというものである。現行の一定限度の利子非課税に比べて、拠出段階で税制の優遇を設けることによって、勤労者の拠出に対するインセンティブを高めるのが狙いである。また、現行の事業主の財形給付金の上限を緩和し、勤労者拠出分と合わせて退職時に給付する。給付形態は、原則年金としつつ一時金受け取りも認めることとし、給付時の税制上の取扱いを退職一時金、退職年金と同様にすることを提案している。
案2は、勤労者拠出分の税制上の取扱い、事業主拠出分の制限緩和、給付形態及び給付時の税制上の取扱いについては案1と同様だが、勤労者個人と金融機関等が契約を行っていたものを、企業又は財形基金が、運用方法の選択肢毎に勤労者の拠出分をとりまとめ、金融機関等と契約を行うこととしている。また、事業主の任意の拠出分については、労使の合意を前提に、勤労者の拠出部分と一括して運用することもできる形にしている。これによって、運用の幅が広がり、運用コストが軽減される可能性が高まると考えられる。
参考案は、企業からの給付を、現時点で給与として受け取るか、退職時まで受け取りを据え置くかを勤労者が選択し、据置を選択した部分については、事業主が事業主拠出金として積み立てるという考え方である。最近の事例として注目されている退職金を給与として受け取ることを認める制度の受け皿としても機能する面があると考えられる。
これらの案は、財形年金貯蓄制度再編の方向性を含め、「勤労者拠出型年金制度」の太枠を示したものであるが、実際の制度再編にあたっての移行方法や細部取扱い等の課題については、さらに検討を進めることが必要であろう。
ページ先頭に戻る
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
勤労者拠出型年金制度研究会 委員
<委員>
村上 清 ◎年金評論家
高山 憲之 一橋大学経済研究所教授
陶野 哲雄 タヮーズペリン プリンシパル
藤田 伍一 一橋大学社会学部教授
吉牟田 勲 東京経営短期大学経営税務学科教授
<オブザーバー>
久保田秀一 日本生命法人業務部担当部長兼企業保険契約部担当部長
<研究担当>
森茂雄ニッセイ基礎研究所生活研究部長ほか主任研究員など4名
(◎は座長)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(注)報告書で、機種依存文字A.、B.となっている部分は、A,Bに変更してあること。
■GO HOMEPAGE
■GO 640/480
■福利厚生制度の総目次へ